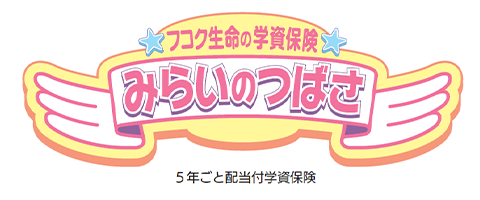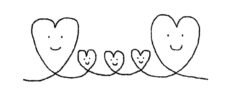- 保険
- 学資保険
学資保険は3歳からでも遅くない!3歳から学資保険を始めるメリットと注意点


「3歳から学資保険に入るのは遅い?」
「3歳から学資保険に入るときの注意点は?」
子供が3歳から学資保険に加入しても遅くありません。3歳から積み立てを開始しても、高校や大学など進学に必要な教育資金の準備に間に合います。
ただし、3歳からの加入によるデメリットもあるため、慎重な検討が必要です。
本記事では学資保険を3歳から始めるメリットや注意点について紹介します。
この記事の監修者
-
 有岡 直希
有岡 直希ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。- <保有資格>
- AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士
- この記事の編集者
- 最新記事
- グッドカミング編集部
- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。
- 未経験でも年収交渉は可能?面接で失敗しない伝え方と成功させるための準備 2026.02.24
- 保護中: 12星座別 2026年3月の運勢【占いの館 千里眼】桂(かつら)先生月間連載 2026.02.24
- 定期保険は年末調整で控除できる?控除を受ける流れを初心者向けに解説! 2026.02.20
この記事の目次
学資保険は3歳からでも加入できるのか
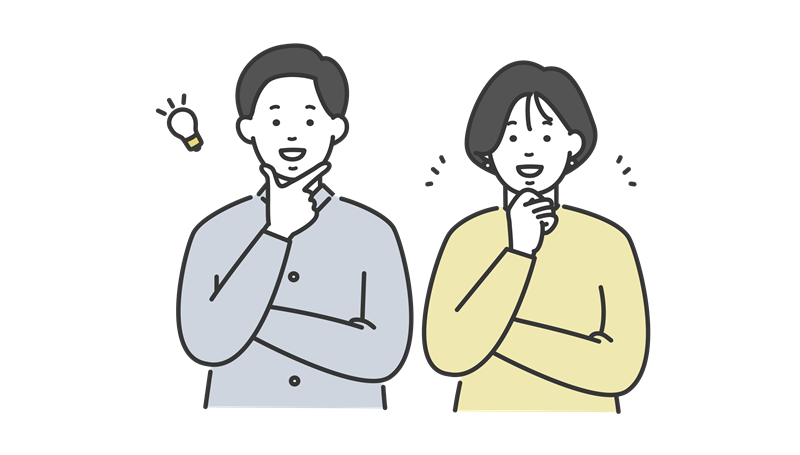
3歳から学資保険に加入できるか説明します。
学資保険の年齢制限と条件
学資保険の加入には年齢制限が設けられていて、6歳までを対象とする商品が多いです。
3歳からでも加入できる学資保険は豊富にあり、たくさんの商品から選べますが、保険会社や商品により学資保険の加入条件の違いは大きいです。
3歳からの加入で間に合う教育費目安
学資保険は17歳や18歳、22歳などを満期とする商品が多いです。
3歳からの加入でも10年以上の長期に渡り保険料を支払い続ければ大学進学に必要な教育費の確保に間に合います。
学資保険の中には小学校や中学、高校など進学に応じて祝い金を受け取れる商品も多いです。
3歳からの加入でも、小学校や中学、高校入学時に給付金を受け取れる商品であれば、それぞれのタイミングで進学に必要な資金を準備できます。
返戻率が下がる理由と仕組み
学資保険に3歳から加入すると保険会社の運用期間が短くなるため返戻率は下がりやすいです。保険会社は契約者の支払った保険料を運用して利益を得ています。
運用期間が長いほど多くの運用益が発生し、契約者に還元される仕組みです。
学資保険の加入が遅くなるほど運用期間が短くなるため、返戻率は下がるでしょう。
ただし、返戻率は、保険料の払込期間や給付時期、月々の保険料などにも左右されます。契約時の条件次第では3歳からの加入でも返戻率を高くするのは可能です。
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2026年01月01日~01月31日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。
学資保険を3歳から始めるメリット
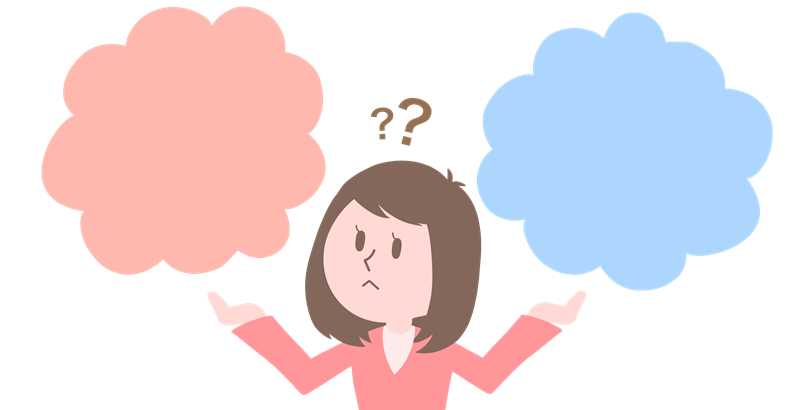
3歳から学資保険に加入するメリットを紹介します。
教育費を計画的に準備できる
3歳から学資保険を始めれば将来の教育費を計画的に準備できます。学資保険は毎月決まった額の保険料を積み立てると所定の時期にまとまった給付金を受け取れる商品です。
大学入学など大きな教育費の発生する時期に備えられます。
保険による保障が得られる
学資保険は契約者の死亡や高度障害時には以降の保険料が免除されるのが特徴です。保険料が免除されても、保険料が払い込まれた場合と同額の祝い金や満期保険金を受け取れます。
単に教育費の積み立てができるだけではなく、残された家族を守る役目も果たせるのが学資保険の魅力です。
貯蓄型で確実に資金が貯まる安心感がある
学資保険は貯蓄型の商品であり、毎月積み立てていき、満期にまとまった給付金を受け取れる商品です。解約しなければ積み立てた資金を使えないため、途中で利用する心配はありません。
毎月の保険料や給付時期などは契約時に決められるため、計画的に教育資金を準備できます。教育資金を集める方法として確実性があり、安心感のある商品が学資保険です。
学資保険を3歳から始めるデメリットと注意点

学資保険を3歳から始める場合のデメリットや注意点を紹介します。
返戻率が低くなる可能性
学資保険への加入が遅くなると返戻率が低くなる傾向があります。加入のタイミングが遅いと運用期間が短くなって運用益が増えにくくなるからです。
返戻率が低いと支払った保険料の総額に対して給付される金額が減り、元本割れが起きるリスクがあります。
払込期間が同じでも、商品によって返戻率の違いは大きいです。学資保険を選ぶ際には返戻率を比較しましょう。
保険料の負担が大きくなる場合がある
加入時期が遅くなると払込期間が短くなり、保険料の負担が大きくなりやすいです。同じ給付額を目指す場合、払込期間が短いほど月々の保険料が高くなります。
3歳から学資保険に加入する場合は、保険料の負担が家計に与える影響について考慮するのがポイントです。無理のない保険料の支払いを実現するために払込期間の延長や給付額を減らすなどを検討しましょう。
他の貯蓄方法との比較が必要
貯蓄方法には、学資保険以外にもつみたてNISAの活用や銀行の定期預金など多くの選択肢があります。
教育資金を確保する方法を比較して、ライフプランに合った方法を選びましょう。
それぞれの方法のメリットやデメリットを比較し、最適な選択をすれば、教育資金の確保に失敗するリスクを軽減できます。
学資保険を3歳から始める際の選び方

3歳から学資保険に加入する際の商品の選び方を紹介します。
返戻率が高い商品を選ぶポイント
返戻率が高いほど支払った保険料に対して多くの給付金を受け取れる仕組みです。
返戻率が高く設定されている商品を選べば、より多くの給付金を受け取れるでしょう。
ただし、返戻率は保険料の払込期間や受給するタイミングなどで変わるため、単純に返戻率を比較するだけでは不十分です。
学資保険は、払込期間や受給するタイミングなどの選択肢が豊富な商品を選びましょう。払込期間や受給の時期を調整すれば、返戻率を上げられます。
保障内容と貯蓄性のバランスを確認
学資保険は、保障が充実した商品や貯蓄性を重視した商品までさまざまです。
保障が手厚い商品は返戻率が低く満期に受け取れる金額が少なくなる傾向にあります。貯蓄性が高い商品は保障内容が最低限の場合が多いです。
保障内容と貯蓄性のいずれを重視するのか踏まえた上でバランスの取れた商品を選びましょう。
支払い期間や給付時期を検討する
学資保険の支払期間は毎月の保険料や返戻率に影響を与えます。支払期間が短いと返戻率が高くなるのですが、月々の保険料の負担が大きいです。
給付時期は、小・中・高・大の入学時に祝い金として受け取る方法や大学入学時にまとめて受け取る方法などがあります。給付金を受け取るタイミングが遅いほど運用期間が長くなり返戻率は上がりやすいです。
返戻率や保険料の負担などを考慮した上で支払期間や給付時期を検討しましょう。
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2026年01月01日~01月31日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。
学資保険以外の教育資金準備法も検討しよう

学資保険以外にも教育資金の準備に適した方法はあります。学資保険と他の方法を組み合わせるとさまざまなリスクに備えられるでしょう。学資保険以外の選択肢について詳しく紹介します。
つみたてNISAを活用する
教育資金の準備方法としてつみたてNISAがあります。つみたてNISAは年間投資枠の範囲内であれば運用益が非課税になる投資制度です。
長期的に運用して高いリターンを目指せる方法であり、上手くいけば効率的に資産運用を行い教育資金の確保ができます。
ただし、つみたてNISAには元本保証がないため、元本割れで教育資金が不足するリスクがある点に注意しましょう。
低解約返戻金型の終身保険
近年、低解約返戻金型の終身保険を学資保険の代替手段として利用される方が増えています。
● 返戻率が比較的高く、計画的に積み立てることで進学時に一定の資金を準備できる。
● 教育資金として使わなかった場合でも、解約せずにそのまま終身保険として継続保有でき、将来的な保障の確保や資産形成の手段として活用の幅がある。※学資保険は選択肢がない
学資保険は3歳からでも教育資金準備に有効
3歳から加入したとしても学資保険で教育資金を準備できます。学資保険は単に教育資金を貯めるだけではなく万が一の保障もある商品です。
ただし、加入時期が遅いと返戻率が低くなり、保険料の負担が大きくなる可能性があります。メリットとデメリットを理解し、他の方法も踏まえた上で学資保険の加入を検討しましょう。