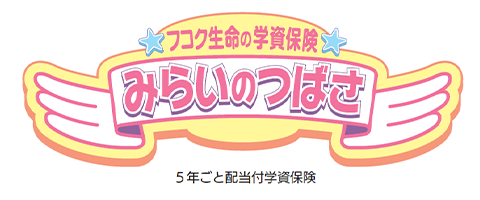- 保険
- 学資保険
公務員でも学資保険に入るべき?公務員の学資保険加入メリットと判断基準


「公務員に学資保険は必要ない?」
「公務員が学資保険位入るメリットは?」
将来の教育費を備えるために効果的な選択肢が学資保険です。安定した収入のある公務員でも学資保険に入るメリットはあります。
学資保険の加入により不足の事態に備えられ、返戻率によっては保険料を上回る給付金を得られるからです。
本記事では公務員が学資保険に加入するメリットや判断基準などを紹介します。
この記事の監修者
-
 有岡 直希
有岡 直希ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。- <保有資格>
- AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士
- この記事の編集者
- 最新記事
- グッドカミング編集部
- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。
- 定期保険は年末調整で控除できる?控除を受ける流れを初心者向けに解説! 2026.02.20
- オファー面談で年収交渉は可能?エージェントを活用するメリットとコツも解説 2026.02.20
- 結婚しない娘と同居中…このままでいいのか迷う親が知るべき現実と具体策で娘さんの婚活をサポート 2026.02.19
この記事の目次
公務員でも学資保険は必要なのか?

公務員に学資保険が必要なのか解説します。
安定収入でも教育費は大きな負担
安定収入が保証される公務員であっても、教育費の負担は大きいです。
教育費は大学進学まで含めると1,000万円以上かかるケースがあります。収入が安定している公務員でも教育費への備えは必要です。
貯蓄だけで足りないリスクに備える
公務員に学資保険が必要な理由は、貯蓄だけで教育資金が不足するリスクに備えられるから。
病気や怪我、事故などで想定外な出費が重なると貯蓄の計画が崩れる可能性があります。
学資保険は、毎月一定額を積み立てていき、進学するタイミングで給付金を受け取れる仕組みです。計画的な貯蓄が苦手な人でも、学資保険であれば自動で引き落とされるため、着実に教育資金を準備できます。
学資保険は教育資金を計画的に準備できる手段
計画的に教育資金を準備するのに学資保険は最適な手段です。
学資保険は特定のタイミングに給付金を受け取れるように毎月積み立てていく仕組みとなっています。高校や大学進学などの時期に合わせて必要な教育資金の準備が可能です。
学資保険は適用される返戻率が高ければ支払った金額以上の給付金を受け取れる可能性があります。将来の高額な教育費の負担に計画性を持って備えられるのが学資保険です。
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2026年01月01日~01月31日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。
公務員に学資保険が不要と言われる理由

なぜ公務員に学資保険が不要と言われるのが理由を紹介します。
共済組合による貸付制度がある
公務員は共済組合の提供する貸付制度を利用できます。貸付制度により教育資金を低金利で借りられるため、学資保険がなくても資金の準備が可能です。
福利厚生で教育資金がある程度カバーできる
公務員は福利厚生が比較的充実しており、自治体によって独自の福利厚生制度が用意されている場合もあります。
ただし、福利厚生だけですべての教育費のカバーは不可能です。学資保険や貯蓄などによる備えも必要になります。
貯蓄で十分に備えられるという見方も
公務員の安定した収入があれば、計画的な貯蓄で十分な資金を用意できるとも考えられます。預金や投資などの方が資金として柔軟性が高いケースも。
リスクマネジメントの観点では、複数の方法の併用が効果的です。貯蓄のみで教育資金を備えられる人でも、学資保険を検討する価値はあります。
公務員が学資保険に入るメリット

公務員が学資保険に加入する主なメリットを紹介します。
確実に教育資金を貯められる安心感
毎月の積み立てさえ行えば将来的に決まった額の教育資金を貯められる安心感があるのが学資保険です。
積み立てた資金は解約しなければ途中で使うことはなく、計画性を持って教育資金を準備できます。
高校や大学などの進学時期に合わせて給付金を受け取れる仕組みのため、入学金や授業料など高額な支払いに備えられるのが学資保険の魅力です。
払込免除特約で万が一にも備えられる
学資保険には、契約者の死亡や高度障害状態などで保険料が免除される「払込免除特約」が付加されるのが一般的です。
不測の事態で世帯収入が激減したとしても、払込免除特約のおかげで将来の教育資金を確保できます。万が一のリスクに備えながら教育資金を準備できるのは学資保険の魅力の1つです。
保険ならではの返戻率で増やす効果も
学資保険の返戻率によっては支払った保険料を上回る給付金を受け取れます。単にお金を貯めるだけではなく、増やす効果を期待できるのが学資保険のメリット。
ただし、返戻率は保険商品や満期までの期間、保障内容などにより変わります。事前に返戻率と満期で受け取れる金額を確認しておきましょう。
公務員が学資保険を検討する際の注意点

公務員が学資保険の加入を検討する上で注意したい点を紹介します。
返戻率は加入のタイミングで大きく変わる
返戻率は加入する年齢や払込期間などで大きく変動します。満期までの期間が長いほど返戻率も高くなる仕組みです。
子供が小さい頃に加入すれば返戻率が高くなり、より多くの教育資金を準備できます。
バランスを考えて加入額を決める
学資保険の加入は収入や貯蓄とのバランスを考えた上で決めるのが大事です。
学資保険ですべての教育資金を準備する必要はありません。毎月の支払いを満期まで続けられるように保険料は必要最低限に留めておくと良いでしょう。
途中解約すると元本割れのリスクがある
学資保険は満期まで積み立てるのを前提とした商品のため、途中解約すると元本割れのリスクがあります。元本割れすれば学資保険の加入で損失が発生するため、途中解約はできるだけ回避するのがベスト。
日々の生活に必要な資金を踏まえた上で、教育資金に振り分けられる資金の範囲内で保険料を設定しましょう。
夫婦ともに公務員ならどちらの名義で契約するか検討が必要
夫婦がともに公務員の場合は、学資保険の名義をどちらにするか決めなければいけません。
払込免除特約が適用されるのは契約者のため、万が一のリスクが起きる可能性の高い者の名義で契約するのが望ましいです。
収入や勤務状況、将来のライフプランなども踏まえた上で契約者の名義を決めましょう。
低解約返戻金型の終身保険も検討してみる
近年、低解約返戻金型の終身保険を学資保険の代替手段として利用される方が増えています。
● 返戻率が比較的高く、計画的に積み立てることで進学時に一定の資金を準備できる。
● 教育資金として使わなかった場合でも、解約せずにそのまま終身保険として継続保有でき、将来的な保障の確保や資産形成の手段として活用の幅がある。※学資保険は選択肢がない
学資保険以外の方法もありますので、悩んだらFPへの相談もおすすめです。
公務員におすすめの学資保険の選び方

公務員が最適な学資保険と契約するためのおすすめの選び方を紹介します。
返戻率が高い商品を比較する
基本的に学資保険は返戻率の高い商品が望ましいです。返戻率が高ければ、支払った保険料よりも多くの給付金を受け取れます。
返戻率が高い商品の中から特約や払込期間、保険料などの条件を比較すれば、最適な商品を選べるでしょう。
払込期間を短く設定できるか確認する
学資保険の払込期間を短く設定できる商品を選ぶと、子供が小さいうちに保険料の支払いを終えられます。
教育資金の準備が早期に終われば、家計への負担を軽減できるでしょう。
払込期間が短いと保険会社が運用できる金額が多くなり、運用期間も長くなるため、返戻率は高くなる傾向にあります。
家計に余裕があるならば、払込期間の短い商品を検討しましょう。
医療特約や育英年金特約の必要性を見極める
学資保険の契約で医療特約や育英年金特約を付けると保障が手厚くなります。ただし、特約が増えるごとに保険料が上がり、支払いの負担が大きくなるため、必要性を見極めるのが大事です。
既存の保険でカバーできている保障は不要なため、最小限の特約のみを付けましょう。
公務員でも学資保険は教育資金準備の有効な手段
公務員は安定した収入があり教育資金に備えやすいです。ただし、教育費用は高額になりやすいため、公務員であっても学資保険の加入は有効な選択肢となります。
貯蓄や共済制度と学資保険を併用すれば、少ないリスクで教育資金の準備が可能です。子供の教育資金を準備する方法として学資保険を上手く活用しましょう。