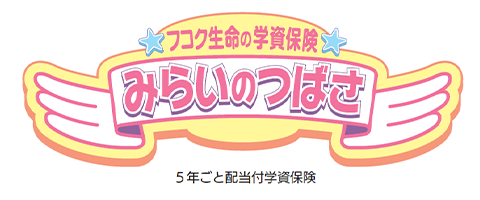- 保険
- 学資保険
学資保険の払込期間とは?払込期間を短くして保険料の支払総額を抑えよう


「学資保険の払込期間はどうすればいい?」
「払込期間は短いほうがいいの?」
学資保険の契約にあたり、払込期間をどうするか悩む方も少なくありません。
払込期間は複数パターン選べますが、払込期間が短いと返戻率が高くなりやすいです。
この記事では学資保険の払込期間について基本から選び方、注意点までやさしく解説。
学資保険の払込期間をどうするか迷っている方、必見です!
この記事の監修者
-
 有岡 直希
有岡 直希ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。- <保有資格>
- AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士
- この記事の編集者
- 最新記事
- グッドカミング編集部
- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。
- 定期保険は年末調整で控除できる?控除を受ける流れを初心者向けに解説! 2026.02.20
- オファー面談で年収交渉は可能?エージェントを活用するメリットとコツも解説 2026.02.20
- 結婚しない娘と同居中…このままでいいのか迷う親が知るべき現実と具体策で娘さんの婚活をサポート 2026.02.19
学資保険の払込期間とは
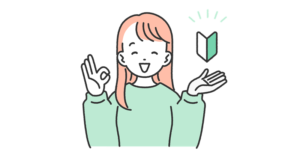
払込期間とは、学資保険の保険料を払い終えるまでの期間を指します。
期間は一括、短期、長期など複数のパターンから選べる仕組み。
払込期間は契約時に設定でき、契約途中では基本的に変更できません。
家計やライフステージの変化を考慮して、払込期間を設定しましょう。
学資保険の払込期間の種類

1.短期払と長期払
払込期間について考える際には、「短期間で払うか長期間で払うか」を検討しましょう。
両者の傾向をまとめてみました。
| 項目 | 短期払 | 長期払 |
|---|---|---|
| 月額保険料 | 高くなりやすい | 抑えやすい |
| 返戻率 | 高め | やや低め |
| 支払総額 | 抑えやすい | 高くなりやすい |
| 支払期間 | 短い | 長い |
払込期間が短いと月額保険料は高くなりますが、支払いは早く終わるため、その後の家計が楽になるのは大きな利点。
短期の方が返戻率が高くなりやすく、一時的な負担増と引き換えに効率的な資金形成を期待できます。
払込期間が長いほど月額保険料は抑えられますが、トータルの支払額は増加傾向が。
返戻率も低くなる傾向なので、資産形成にはつながりにくいでしょう。
どちらにもメリットとデメリットがあるため、家庭の資金計画を踏まえて検討してください。
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2026年01月01日~01月31日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。
2.一時払い
学資保険の保険料払込方法には、一時払いもあります。
一時払いは、契約時に保険料の全額を一括で支払う方法です。
払込期間が契約時に完了するためその後の家計への影響がなくなるうえに、返戻率が最も高くなりやすいのが大きな魅力。
一時的に大きな出費を伴うため、資金に余裕がある方向けの手段です。
3.全期前納の選択肢も
全期前納とは、保険料の全額をまとめて契約時に保険会社へ預ける払込方法です。
預けた保険料は、月や年単位で保険料として充当されていきます。
一時払いと混同されやすい方法ですが、全期前納では解約時にまだ充当されていない分を返還してもらえるのが大きな特徴です。
学資保険の払込期間を決める判断基準

✅ 教育費のピークを見越す
学資保険の払込期間を検討するうえでは、教育費のピークタイミングを見越しましょう。
教育費が増加しやすいのは、一般的に高校・大学進学のタイミングです。
払込期間をそれ以前に終える設計にすれば、出費が重なるリスクを避けやすくなります。
教育費のピークを見据えた設計が、安定した家計を支えます。
✅ 収支バランスを考慮する
保険料が家計に与える影響は、毎月の収支で大きく変わります。 固定費を増やしすぎると、生活全体にゆとりがなくなりがち。
項目を整理して考えるといいでしょう。
- 毎月の余剰資金(貯金可能額)
- 他の固定費(住宅ローン、習い事など)
- 臨時支出の頻度(旅行、家電購入など)
払込期間は長期にわたるケースも多いため、家計の収支を考えた無理のない支払い計画を立てましょう。
✅ 保障内容とのバランスをとる
保障が手厚いと払込期間が長くても月額保険料が高くなりやすいため、保障内容とセットで考えましょう。
学資保険の中には、保険料払込免除などの保障がついたタイプもあります。
「保障」と「貯蓄性」のどちらを重視するのかによって、最適なプランは変化。
保障内容と負担のバランスが取れた、無理のない設計を心がけましょう。
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2026年01月01日~01月31日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。
✅ 払込期間終了年齢で選ぶ
学資保険では、以下のように払込終了年齢を基準にした設計も見られます。
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 10歳払済 | 小学校卒業までに払込終了 |
| 15歳払済 | 中学校卒業を目安に払込終了 |
| 18歳払済 | 高校卒業時点で払込終了 |
払込終了年齢を基準にすると、将来のライフイベントに合わせた支払いスケジュールの調整がしやすくなります。
払込期間の選択は、ライフプランへの影響が大きく、先々の出費を見越した設計が長期的な安心につながるでしょう。
たとえば、下の子どもの出産や住宅ローンとの兼ね合いも考慮が必要。
支払いが生活を圧迫しないよう、全体のバランスを整えましょう。
学資保険の払込期間で注意すべき点

返戻率も意識する必要がある
払込期間と同時に返戻率も考慮しましょう。
払込期間を長く取りすぎると、保険会社の運用期間が短くなるため返戻率が大きく下がる傾向があります。
返戻率を重視するなら、なるべく早めに支払いを終える設計が理想といえるでしょう。
返戻率を重視するなら、払込期間の設計がカギを握ります。
保障期間とのズレに注意
学資保険には、保険料を払い終える「払込期間」と、保障が続く「保障期間」があります。
同じように見えても、ぴったり一致するとは限りません。
契約前に、満期のタイミングや保障がいつまで続くのかをしっかり確認しておきましょう。
途中解約による損失
契約期間中に保険を解約すると、元本割れしやすくなります。
支払いが不安定な家計では、保険料支払いを続けられず途中で解約する可能性も。
以下のような状況があるなら、慎重な判断が求められます。
- 収入が不安定な職種
- 生活防衛資金が不足している
- 近い将来に大きな支出予定がある
継続できる見通しを立てたうえで、学資保険の契約をしましょう。
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2026年01月01日~01月31日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。
【まとめ】学資保険の払込期間は将来を見据えて選ぼう
学資保険の払込期間は、家計にも大きな影響を与えます。
短期払いや一括払いは返戻率が高くなる反面、月々の負担が重くなる特徴があります。
一方で長期払いは月額を抑えやすいものの、最終的な支払総額が増えやすくなる設計。
家庭の収支やライフプランを踏まえて、無理のない範囲で効率よく設計しましょう。
合わせて医療保険などの見直しを考えている方は、見積もりシミュレーションをしてみるといいでしょう。