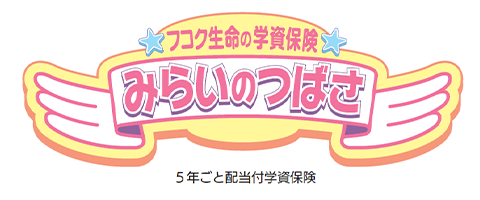- 保険
- 学資保険
学資保険はおすすめしないのはなぜ?リスクを減らして教育資金を準備する方法


「学資保険をおすすめしない理由は?」
「学資保険のデメリットが知りたい」
学資保険を検討するからこそ、「おすすめしない」といった記事や評判が気になる方も少なくありません。
学資保険をおすすめしない理由は返戻率の低さや元本割れのリスクが考えられますが、自分に合った商品を選んで早めに加入すれば教育資金をしっかり準備できます。
この記事では、学資保険をおすすめしない理由やデメリットを解説。
学資保険に入るべきか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
この記事の監修者
-
 有岡 直希
有岡 直希ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。- <保有資格>
- AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士
- この記事の編集者
- 最新記事
- グッドカミング編集部
- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。
- 定期保険は年末調整で控除できる?控除を受ける流れを初心者向けに解説! 2026.02.20
- オファー面談で年収交渉は可能?エージェントを活用するメリットとコツも解説 2026.02.20
- 結婚しない娘と同居中…このままでいいのか迷う親が知るべき現実と具体策で娘さんの婚活をサポート 2026.02.19
この記事の目次
学資保険はおすすめしない?デメリットは

学資保険は教育資金の積み立てを目的とした保険で、一定期間保険料を払い続ければ満期時に保険金を受け取れます。
着実に教育資金を貯められるだけでなく、契約者に万が一があっても保険料負担が免除される「払込免除特約」を付けられるのも魅力です。
では、「おすすめしない」「いらない」といわれる理由はどこにあるのでしょうか。
返戻率が低い
学資保険の多くは貯蓄型ですが、期待される返戻率(支払った保険料に対する保険金額の割合)はあまり高くありません。
低金利の影響から返戻率の水準が低くなっているのが近年の傾向で、定期預金とほとんど変わらない返戻率の商品もあります。
学資保険はあくまでも教育資金を計画的に準備する手段であり、一方で実質的な利益はあまり期待できないと考えておくべきでしょう。
途中解約で元本割れのリスク
学資保険には、途中でやめると元本割れ(戻ってくる金額が支払った保険料より少なくなる状態)のリスクがあります。
たとえば、急な収入減や生活の変化で解約すると元本割れが大きなリスクに。
保険は長期間にわたる契約が前提なので、途中での見直しがしづらいのが難点です。
柔軟性に欠ける点からも、おすすめしないと考える人もいます。
自由に引き出せない
学資保険を契約すると、基本的には満期まで積み立てている保険料を引き出せません。
もし急にお金が必要になっても保険金の事前受取はできないため、途中解約して返戻金を受け取るしかありません。
使い道の自由度を重視するなら、学資保険はおすすめしないと言えるでしょう。
受取時に税金が発生する可能性がある
保険料を支払った人と保険金の受取人が異なると贈与税の対象になるため、受取時に課税される可能性もあります。
具体的には受け取った金額から基礎控除である110万円を差し引いた額が課税対象です。
保険契約者と受取人が同じでも、所得税の対象になるケースが。
契約内容によって課税の有無や金額は異なり、契約時には税金も考慮する必要があるためおすすめしないと考える人もいます。
課税対象にならない範囲で学資保険の積み立てをしたい方は、保険のプロへの相談を検討してみるのも◎
グッドカミング公式LINEでは保険のプロにいつでも相談できるので、ぜひ参考にしてください。
学資保険をおすすめしない人の特徴

柔軟に教育資金を準備したい人
学資保険は満期まで引き出せないため、途中で資金を使いたい人には不向きです。
たとえば、子どもが中学や高校で留学を希望してもすぐ対応できないケースが。
普通預金やNISAなら、必要なタイミングで資金を動かせますが、自由度を重視する人にとって、学資保険は使いにくさを感じやすい金融商品です。
予定外の支出にも柔軟に対応したい人は、別の選択肢を考えたほうが安心でしょう。
投資や運用に前向きな家庭
「教育費を効率よく増やしたい」と考える家庭には学資保険の利回りは物足りないでしょう。
NISAや投資信託などを使えば、時間をかけてお金を増やす選択肢が広がります。
学資保険は保守的で安定性はありますが、運用益を求める人にとっては不利です。
投資に前向きな家庭であれば、学資保険より柔軟で成長性のある方法を選んだほうが合理的といえます。
収入や家計の変動が大きい家庭
学資保険は毎月決まった保険料を支払うため、収入が不安定な家庭には向いていません。
仕事の都合で収入に波があり、保険料を滞納すると保障が失われるリスクもあります。
一時的な家計の変化にも対応しにくく、柔軟性が求められる家庭にはリスクが高いため、収入の変動が大きい人は自由度の高い資金管理方法を選ぶほうが安全です。
学資保険をおすすめしない人と
する人の違い
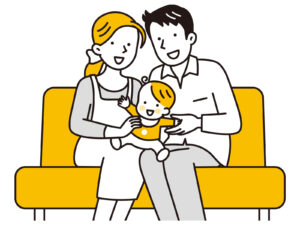
計画的に教育費を貯めたい人
学資保険は毎月決まった金額を積み立てて教育費を準備するため、コツコツ貯めるのが得意な人にとっては計画的に資金を蓄えられる安心感があります。
自動引き落としによって、強制的に積み立てができるのも魅力のひとつ。気づいたらお金を使ってしまう人には、貯金の習慣をつける手段になります。
そのため、計画的に貯められる人にとっては「学資保険をおすすめしない」評価は当てはまりにくいです。
元本割れを避けたい堅実な家庭
投資のように価格が変動する商品ではなく、安定した貯蓄手段を望む人にとって学資保険は選びやすいです。
満期まで契約を続ければ、受取額がほぼ確定しているため大きなリスクがありません。
預けたお金を減らしたくないニーズがあるなら、学資保険の仕組みは安心材料になるため、慎重に資金を管理したい家庭には適しているといえるでしょう。
このように、元本割れを絶対に避けたい人には「学資保険をおすすめしない」意見は当てはまりにくいです。
保険を利用した備えに
安心感を求める人
学資保険には、保障がセットになっている特徴もあります。
親に万が一があっても、保険会社が残りの保険料を支払う制度があるため確実に教育資金が用意できます。
将来のリスクに備えておきたいと考える家庭にとっては、大きな安心につながります。
「保険」としての側面に価値を感じる人にとっては、他の貯蓄方法とは違うメリットがあるのです。
保障に安心を求めるタイプの家庭にとっては、「学資保険をおすすめしない」判断は当てはまりにくいでしょう。
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2026年01月01日~01月31日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。
学資保険をおすすめしないと
判断できる根拠
返戻率や保険料を具体的に
シミュレーション
学資保険を検討する前に、返戻率や保険料を具体的にシミュレーションしてみましょう。
シミュレーションをすると、実際にどれだけ増えるのかが数字で見えてきます。
商品によって返戻率が100%を下回る結果を見て「おすすめしない」と判断する人もいます。
ほかの貯蓄・投資商品と比較して判断
学資保険だけでなく、つみたてNISA、定期預金など他の手段とも比較してみましょう。
それぞれの利回りや使いやすさ、流動性を比べると、自分に合った方法が見つかります。
学資保険は元本保証がある反面、柔軟性に欠ける弱点があります。
一方、NISAは資金の出し入れが自由で、増やす力も期待できます。
家庭の資金計画に合うかを見極める
どんなに評価が高い商品でも、自分の家庭に合っていなければ意味がありません。
学資保険が毎月の支出に大きな影響を与えるなら、家計にとってリスクになります。
保険料を無理なく払い続けられるか、他の支出と両立できるかを冷静に確認を。
必要なタイミングでに教育費が用意できるかどうか、ライフプラン全体で考えましょう。
「他人がすすめているから」ではなく、「自分に合っているか」を判断の軸にしてください。
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2026年01月01日~01月31日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。
【まとめ】学資保険をおすすめしない理由を理解し、自分に合う選択をしよう
学資保険は、すべての家庭にとって最適とは限りません。
利回りの低さや資金拘束のデメリットから、学資保険をおすすめしない声も存在します。
投資型制度や定期預金など、柔軟で使いやすい代替手段もあります。
家庭の収入やライフスタイルによっては、保険以外の方法が合うパターンもあるでしょう。
大切なのは、自分たちの家計に合った手段を選ぶこと。
合わせて医療保険などの見直しを考えている方は、見積もりシミュレーションをしてみるといいでしょう。