- 保険
- 終身保険
終活とは?自分らしい人生を整えるため終活をいつからやるべきか解説


「終活とは?何するの?」
「終活はいつから始めるべき?」
「終活」の単語は知っているけれど、抽象的で具体的にどういった内容なのか分からない方も少なくありません。
終活とは身の回りの整理や医療・葬儀の備えも含まれますが、自分らしく生きるための前向きな準備です。
この記事では、終活とは何なのか、基本的な意味や目的、始める時期や具体的な準備まで、初心者にもわかりやすく解説します。
この記事の監修者
-
 有岡 直希
有岡 直希ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。- <保有資格>
- AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士
- この記事の編集者
- 最新記事
- グッドカミング編集部
- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。
- 格安SIMとは?格安SIMの料金が安い理由と仕組み・メリット・注意点を解説 2026.02.17
- HSS型HSPは結婚できないは誤解!不安の正体と幸せになれる結婚相手の特徴 2026.02.16
- ワンルーム投資のサブリースの仕組みは?メリットやトラブルの避け方を解説 2026.02.16
この記事の目次
終活とは?

終活は今後の生き方の前向きな整理
終活とは、人生をより良く生きるための前向きな整理活動です。
「終活」と聞くと、「死に向けた準備」といったネガティブな印象を持つ人も少なくありませんが、これまでの生き方を見直したうえで今後の暮らしを自分らしく整理する目的が。
健康やお金、家族との関係など、終活として取り組むべき内容は多岐にわたります。
身の回り・気持ち・人間関係を見直すライフプラン
終活では物の整理やお金の準備だけでなく、心の整理や人との関係の見直しも重要なテーマ。
「今の暮らしに無駄なものはないか」「誰とどう関わっていきたいか」を考え、その後の人生をより充実させ日々の生活も豊かになります。
自分の価値観を大切にしながら、納得できる生き方を設計していきましょう。
「死」ではなく「安心のための行動」と考える
終活の本質は死を意識した暗い作業ではなく、自分自身と家族の不安を減らすための準備。
自分に万が一があって、保険や医療、財産が整理できてないと家族は混乱してしまいます。
会社の同僚や学生時代の同級生、趣味の仲間などの交友関係を家族が把握できていないと、誰に連絡をすれば良いか混乱するおそれもあるでしょう。
情報を整理しておけば、安心を手に入れられ前向きな行動にもつながっていきます。
終活とは:いつから始めるべき?

終活が一般化した現在、若いうちから取り組む人も増えています。
いつからスタートするのが理想的なのか、具体的な終活の内容を年代ごとに解説します。
40代〜50代:親の介護や将来設計が気になり始める時期
40代・50代といえば親の介護や自身の老後について考えはじめる世代のため、終活をスタートするには良い時期といえるでしょう。
老後までには十分な時間があるため、資産や保険、家族との話し合いなど、無理のない範囲で少しずつ準備を始められます。
仕事に忙しい世代ではありますが、週末などを利用して少しずつ整えていけば負担も少なくて済むはずです。
60代〜70代:自分の体力や健康が変化する時期
定年退職を迎える60代・70代はライフスタイルが大きく変化し体力も大幅に衰えてくるため、終活を本格的に考え始める人が増えます。
生活リズムにゆとりが生まれ、自分の時間を使いやすくなるのもこの年代の特徴です。
不動産や口座の名義変更、相続の確認といった実務的な準備は時間と手間を要するため、ゆとりが生まれる60代以降のスタートもおすすめ。
年齢ではなく「気づいたとき」がベストタイミング
終活を始めるタイミングに正解はありません。
始めるタイミングが早いほど選択肢も多く自分のペースで準備を進められるため、年齢に関係なく「始めよう」と思ったその瞬間が始めどきともいえます。
一方で、70代、80代からでも決して遅くはないため、焦らず自分のペースで取り組んでいきましょう。
終活とは:やること①
資産と身の回りの整理
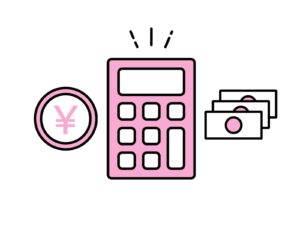
ここからは、終活でやるべき具体的な準備の内容とその方法を解説します。
今すぐにでもできる準備としては、資産や身の回りの整理が挙げられます。
物の整理・断捨離で生活をシンプルに
長年の暮らしの中で増えた物は、老後の生活に思わぬ負担をもたらすおそれがあります。
終活にあたっては、まずは使っていない物や思い出の品の見直しから始めてみましょう。
必要な物だけを残しておけば心も空間もスッキリと整うほか、万が一のときに家族への負担も減らせます。
「今週はこの部屋を片付ける」など、少しずつ取り組んでいきましょう。
通帳・保険・不動産など資産の棚卸し
複数の口座や保険、不動産など、財産が分散していると管理が難しくなるため、一覧にまとめておくと非常に便利です。
ファイルやノートに記載しておけば、自分自身はもちろん家族もすぐに把握できます。
今ある財産をどう使うか考える第一歩として、まずは資産の棚卸しから始めてみましょう。
保険などお金に関する相談がしたいけど、身内や知人には話しづらいと感じる方は、ファイナンシャルプランナーへの相談も◎
グッドカミング公式LINEでは、保険のプロに相談できます。
相続トラブルを避けるための情報管理
終活にあたって大きな不安のひとつが相続時のトラブルです。
資産の棚卸しが完了したら、どの資産を誰にどう分けるかを明文化しておくと家族や親族間のトラブルを防げます。
特に、口座や保険の受取人、借入金の有無などは早めに整理しておくと安心です。
終活とは:やること②
気持ちの整理と家族へのメッセージ

資産や身の回りの整理と同時に、気持ちの整理も欠かせない準備のひとつです。
エンディングノートで希望をまとめる
エンディングノートとは、万が一に備えて自分の想いや希望を書き残すためのノートです。
遺言書のような難しい書類ではないため、終活の第一歩として多くの人に選ばれています。
財産の取り扱いや医療、介護、葬儀の希望はもちろん、家族や親しい人に向けた感謝の気持ちも書き添えておけます。
遺言書などで“もしも”に備える準備
相続や財産の配分についての意思を明確にしておきたい方は、遺言書の作成がおすすめ。
法的効力があるため、希望通りの分配やトラブル防止に役立ちます。
「ありがとう」を伝える
終活は財産や物の整理だけでなく、感謝の気持ちを形にする機会でもあります。
家族や親族、親しい友人などに対し、普段はなかなか言えない「ありがとう」を伝えられれば、より一層心のつながりが深まるでしょう。
手紙やメール、会話の中で感謝を伝えるだけでも立派な終活です。
人生の節目と捉え自分の気持ちをきちんと届ける準備をしてみましょう。
終活とは:やること③
医療・介護・葬儀の準備
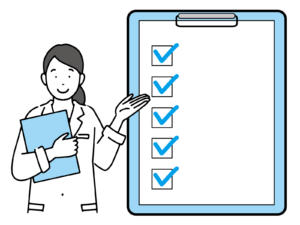
自分に万が一があると、治療や葬儀にはさまざまな手続きが必要であり、残された家族にも大きな負担がのしかかります。
これを軽減するために、少しずつ準備をしておくのも立派な終活にあたります。
延命治療・介護施設の希望を明確に
将来、重篤な病気にかかったときに備え、終末期の治療方針や介護の形について自分の希望を整理しておきましょう。
例えば、治療をしても改善の見込みがない状態に陥ったとき、どこまで延命治療をするかの判断を下すのは家族にとって辛い選択です。
医療保険・終身保険の活用で経済的負担を減らす
医療や介護、葬儀には高額な費用がかかるため、ライフスタイルが変わったタイミングなどで保険の見直しをしておきましょう。
医療保険や終身保険をうまく活用すれば急な出費に備えられ、無理のない老後設計にもつながります。
保険の契約内容はもちろんですが、受取人も定期的に確認しておくと安心です。
自分らしい葬儀のスタイルを考える
最近では、宗教色のない自由な葬儀や、家族だけ参列する小規模なスタイルも増えています。
「どこで・誰に・どのように」見送ってほしいか、自分の希望をまとめておくと家族の負担も軽減されます。
エンディングノートに書いておくだけでも十分に役立つため、具体的な希望があればぜひ記録しておきましょう。
【まとめ】終活とは「自分らしい人生を整える」ための前向きな準備
終活とは人生の不安を減らし、自分らしく生ききるための前向きな準備です。
具体的には、身の回りの整理や資産の見直し、家族へのメッセージや医療・葬儀の備えなど多岐にわたります。
いつ始めても決して遅くはなく、「気づいた今」こそが始めどき。
自分の人生を大切にしながら、できる準備から一歩ずつ取り組んでみましょう。



















