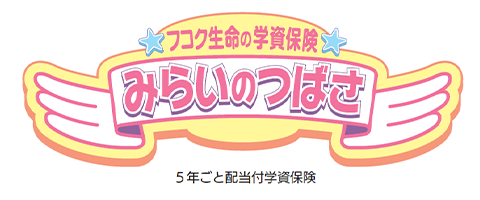- 保険
- 学資保険
【FP監修】学資保険は何歳から入れる?何歳から入るべきか、加入時期とベストタイミングを解説


学資保険は何歳から加入できる?
何歳からの加入がお得?
子の学資保険について、何歳から加入するか迷う方も少なくありません。
何歳から加入できるかは保険会社によりますが、0歳から加入できる学資保険もあります。
この記事では、学資保険に何歳から加入できるか、加入時期ごとのメリットや注意点をわかりやすく解説。
学資保険に何歳から加入するか悩んでいる方、必見です。
この記事の監修者
-
 有岡 直希
有岡 直希ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。- <保有資格>
- AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士
- この記事の編集者
- 最新記事
- グッドカミング編集部
- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。
- 定期保険は年末調整で控除できる?控除を受ける流れを初心者向けに解説! 2026.02.20
- オファー面談で年収交渉は可能?エージェントを活用するメリットとコツも解説 2026.02.20
- 結婚しない娘と同居中…このままでいいのか迷う親が知るべき現実と具体策で娘さんの婚活をサポート 2026.02.19
この記事の目次
学資保険は何歳から加入できるのか
学資保険に何歳から加入できるかは保険会社によっても異なりますが、一般的には0歳~6歳、または7歳までの間であれば加入できます。
保険会社や商品によっては妊娠中から加入できたり、11歳まで受け付けているケースも。
早期からの加入は返戻率が高くなりやすいため、できるだけ早い段階での検討が理想です。
契約者(親)の年齢制限もチェック

学資保険では、契約者となる親の年齢にも制限がある場合が少なくありません。
多くは18歳~60歳前後の範囲に設定されており、年齢が高くなると保険料が割高になる傾向があります。
保険会社によって異なる加入条件

・契約者の健康状態
・保険料払込方法
などは保険会社によって異なります。
加入前には各社から資料請求のうえ条件を比較し、自分たちに合ったプランを選びましょう。
保険会社の数は多く、いきなり比較するのは難しいため保険のプロへの相談がおすすめです。

相談したら必ず契約しなくてはダメですか?
一度持ち帰っていただいて大丈夫です。保険は継続的な支払いが発生するため、納得の上ご契約ください。
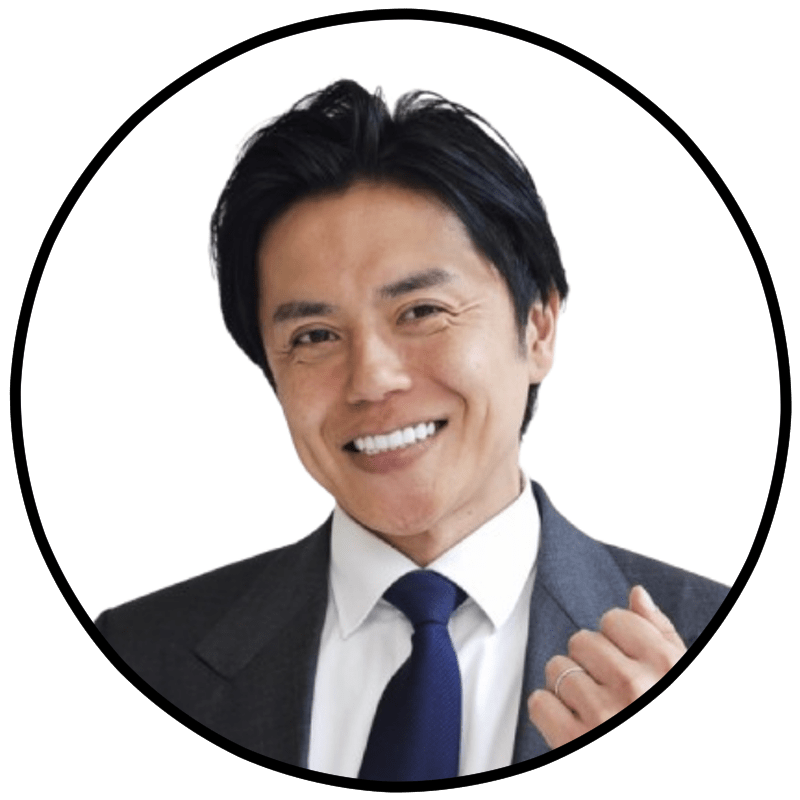
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2026年01月01日~01月31日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。
何歳から入る?:
学資保険早期加入の良い点
学資保険は
✅加入時期が早いほど長く積み立てられる
✅その分返戻率も高くなりやすい傾向がある
といったメリットがあります。
たとえば、0歳からの加入と3歳からの加入とでは3年の差があるため、満期に受け取れる保険金総額に差が出ることも。
効率よく計画的に教育資金を貯めたいなら、早期加入が有利です。
保険料を抑えて長期で積み立てられる
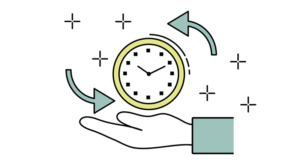
早い段階から学資保険へ加入すると、毎月の保険料が抑えられるのも良い点です。
月々の支出が減るため、家計に大きな負担をかけずに教育資金の準備が進められます。
教育資金を早くから準備できる安心感

生まれてすぐに学資保険に加入しておけば、進学時期に向けて着実に資金を準備でき精神的にも余裕が生まれます。
たとえば、途中で想定外の出費があったとしても、積み立てが確実に進んでいれば子どもの将来を不安視する必要もなくなるでしょう。
学資保険は何歳から加入するか迷ったときの判断ポイント
✅1歳・3歳から加入すると返戻率が下がる可能性

学資保険に0歳から加入した場合と、1歳や3歳になってからの加入を比較すると返戻率が下がるケースがあります。
なるべく高い返戻率を目指すのであれば、加入のタイミングは早いほど有利です。
✅払込期間が短くなると月額保険料が高くなる

加入が遅れると返戻率が下がるばかりではなく、払込期間が短くなる分、毎月の保険料が高くなるおそれもあります。
月々の負担が大きいと家計を圧迫しやすいため、余裕のあるうちに加入を検討しましょう。
✅高校や大学進学時に間に合うか確認が必要

学資保険の返戻金は高校や大学へ入学する年齢に合わせて満期を設定しておき、満期が訪れたタイミングで支払われます。
給付時期と進学時期のズレがないか、事前にしっかり確認しておきましょう。
✅早生まれは準備期間が短くなる

早生まれ(1月~3月)だと、同学年の子に比べて進学時期までの準備期間が短くなります。
学資保険の契約内容によっては、返戻金の給付時期が高校や大学の入学準備に間に合わないケースもあるため注意が必要です。
加入時は誕生月を考慮して、無理のない積立期間と給付時期を設定しておきましょう。
✅親の年齢が高いと保険料が割高になる場合がある

保険料を左右するもうひとつの要因として、契約者である親の年齢が挙げられます。
生命保険と同様、高齢になるほど健康上のリスクが高まるため、それに合わせて保険料が調整されるためです。
保険料を抑えたい場合には、親が若いうちに加入する方が有利といえます。

たとえば契約者である夫が40代で、子が既に3歳の場合は入らないほうがいいですか?
はい、主に「お子様の年齢」がネックです。
3歳だと積立期間が短く、返戻率が下がるので効率が悪くなります。
親が40代でも入れますが、子が3歳なら今から学資保険に入るメリットは小さいです。
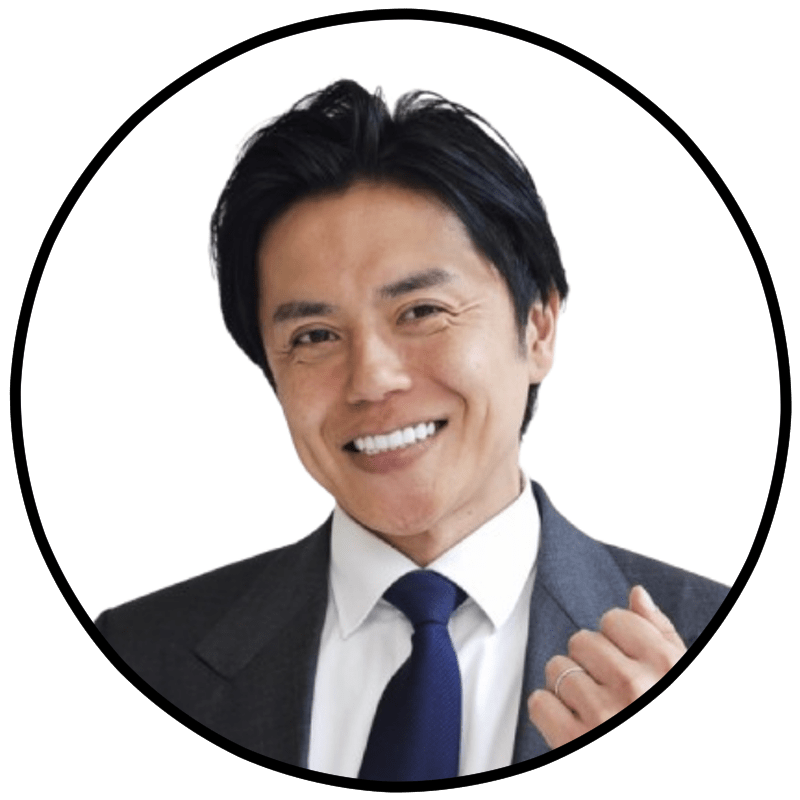
学資保険は何歳からでも加入可能!手続きの流れと注意点
実際に学資保険へ加入するためにはどういった手続きが必要なのか、基本的な流れや加入時の注意点もあわせて解説しましょう。
出生後すぐでも加入できる商品が多い
冒頭でもご紹介した通り、学資保険は生後すぐの新生児でも加入できる商品が多くあります。
出生届提出後であれば申し込み可能なケースも多いため、早い段階から教育資金の準備を始めておけば返戻率や保険料の面でも有利です。
資料請求から契約までの基本ステップ
最近ではオンラインで手続きが完了する保険会社も増えており、忙しい家庭でもスムーズに加入できます。
資料請求や比較検討する時間がない方は、グッドカミングのLINEでの保険相談がおすすめ。
LINEでファイナンシャルプランナーに相談可能で家事の合間やこどもの寝かしつけ中など、いつでも気軽に利用できます。

確認しておくべき保障内容と特約
学資保険は商品によって保障の内容や附帯できる特約が異なります。
主な特約としては
✅契約者に万が一のことがあった際に保険料の支払いが免除される保険料払込免除特約
✅満期まで子が年金を受け取れる育英年金特約
などが代表的です。
特約によっては返戻率が下がるケースもあるため、本当に必要であるか内容をしっかり確認しておきましょう。
学資保険ではなく低解約返戻金型の終身保険を活用するのもあり
近年、低解約返戻金型の終身保険を学資保険の代替手段として利用される方が増えています。
✅教育資金として使わなくても解約せずにそのまま終身保険として継続保有でき、将来的な保障の確保や資産形成の手段として活用の幅がある※学資保険は選択肢がない

終身保険の場合も早めに加入したほうがいいですか?
はい、終身保険も早く入ったほうが得です。
若いうちに入れば保険料が安くて、長く続けるほどお金が増えやすいです。
学資目的なら「早めにコツコツ積み立てる」のがポイントです。
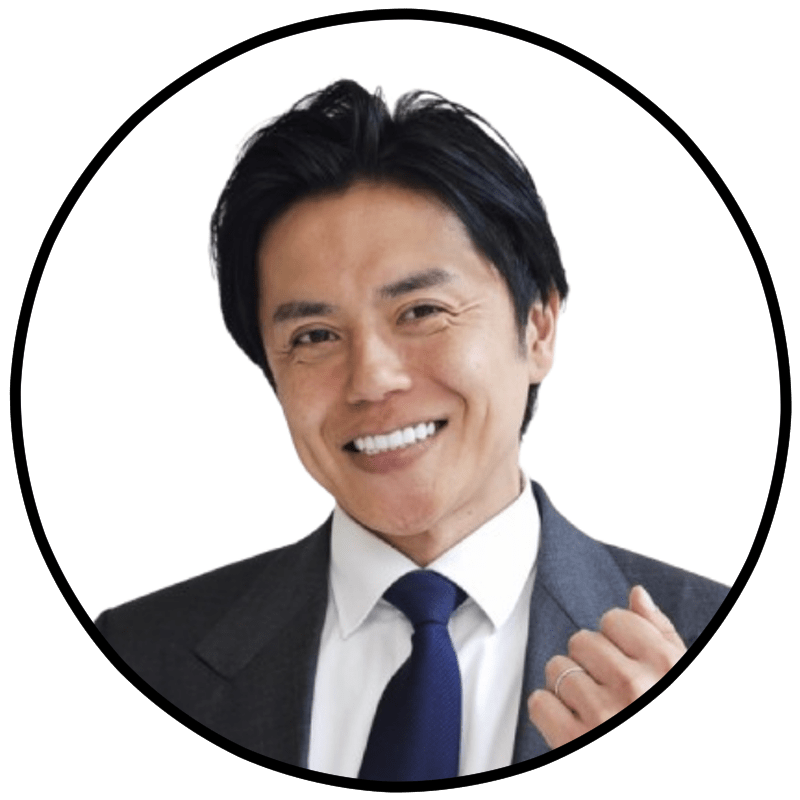
家族構成やライフプランによっても必要な保障のあり方は異なるため、迷っている方は一度保険のプロに相談してみましょう。
学資保険は何歳からでも加入できるが早めが◎
学資保険は0歳から加入できる商品が多く、7歳頃までであれば加入自体は可能です。
ただし、早く加入するほど保険料が抑えられ、返戻率も高くなる傾向があります。
加入時期が遅れると、保険料が高くなるうえに受け取れる給付金の総額も少なくなる可能性があるため注意しましょう。
教育費を無理なく計画的に準備するためには、早めの加入が有利です。
合わせて医療保険などの見直しを考えている方は、見積もりシミュレーションをしてみるといいでしょう。