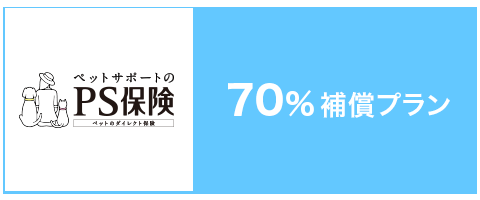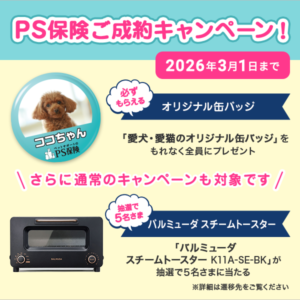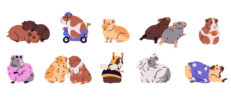- 保険
- ペット保険
マンチカンのかかりやすい病気は?予防対策と注意すべき遺伝性疾患を解説!


マンチカンのかかりやすい病気は?
マンチカンは病気になりやすい猫種?
マンチカンは短い足や丸い顔で人気の猫種ですが、遺伝的に特有の病気が発症しやすいため、定期的な検診や予防が重要になります。
今回は、マンチカンがかかりやすい病気、検査でできる予防や日常的なケア方法などを詳しく解説していきます。
この記事の監修者
-
 有岡 直希
有岡 直希ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。- <保有資格>
- AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士
- この記事の編集者
- 最新記事
- グッドカミング編集部
- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。
- ワンルーム投資のサブリースの仕組みは?メリットやトラブルの避け方を解説 2026.02.16
- 楽天モバイルは対応が悪い?対応が悪いと言われる理由と対処法を解説 2026.02.13
- 【猫好きさんと出会う】50代の猫好きだからこそ見つかる、心地よい出会いのかたち 2026.02.12
マンチカンがかかりやすい病気

椎間板ヘルニア
椎間板ヘルニアは、背骨と背骨の間にある椎間板が本来ある位置から飛び出し、神経を圧迫して痛みや麻痺が発生する病気です。
● 動きがゆっくりになる
● 触られるのを嫌がる
● 足を引きずる、ふらつきがある
● 食欲が落ちる、元気がない
短足のマンチカンは腰に負担がかかりやすく椎間板ヘルニアになりやすい猫種です。
高いところからの飛び降りを防いだり、肥満にならないよう注意し、腰への負担を軽減する対策をしましょう。
骨軟骨異形成症
骨軟骨異形成症はマンチカンの遺伝的な病気で、骨や軟骨が異常に増殖し関節にコブやトゲができたり、指や関節の変形により痛みや腫れが発生する病気です。
● 歩き方がゆっくりになる
● 手足を触られるのを嫌がるようになる
● ジャンプや飛び降りをしなくなる
● 座るときにお尻を地面につけ後ろ足を投げ出す
● 関節が硬く膨らんでいる
● 遊ぶ時間が減り寝ている時間が増える
短足や折れ耳のマンチカンは、骨軟骨異形成症になりやすい遺伝子を持っているため、発症リスクが非常に高い猫種となっています。
骨や関節にできたコブなどが他の骨や筋肉に当たり痛みが出るため、歩行困難やジャンプ拒否、特有の座り方などの症状がみられます。
遺伝的な病気のため根治させる治療方法はありませんが、少しでも猫が元気に過ごせるように症状や痛みの緩和や進行を遅らせるような治療が必要です。
変形性関節症
変形性関節症は、関節に慢性的な炎症が起こったり、関節軟骨を損傷して関節に変形や痛みが発生する病気です。
● 立ち上がるのが遅い
● 動きたがらなくなる
● ジャンプしなくなった
● 足を引きずる、びっこを引いている
● 関節が腫れている、可動域が低下している
● トイレでの排泄が困難になる
● 身体を触られるのを嫌がる
変形性関節症は遺伝的な軟骨形成異常や加齢によって発症しやすく、肥満防止や適度な運動で筋力の維持をするなど、関節に負担がかからない対策をしておきましょう。
外耳炎
外耳炎は、ダニ・アレルギー・耳のケア不足などが原因で、耳の穴から鼓膜までの外耳に炎症が起きる病気です。
● 耳をしきりにかゆがる
● 頭をしきりに振っている
● 耳を触ると痛がる
● 耳から悪臭がする
● 耳に赤みや腫れがある
特に折れ耳のマンチカンは耳の中の通気性が悪く外耳炎になりやすいため、定期的に耳掃除などのケアをしてあげましょう。
肥大型心筋症(HCM)
心臓の筋肉が異常肥大し心臓の血液を送り出すポンプ機能が損なわれ、血液がうっ滞してしまい様々な症状が出る病気です。
● 呼吸が早くなる
● 口を開けて苦しそうに呼吸している
● あまり動きたがらなくなる
● 食欲がなくなる
重症化すると肺水腫や胸水貯留などの合併症を引き起こし、突然死してしまうケースもあるため、早期発見・早期治療が重要となります。
マンチカンは遺伝的に肥大型心筋症になりやすいとされる猫種なので、定期的に心エコー検査などで心臓の健康チェックをしておきましょう。
尿路結石
尿路結石とは、腎臓から尿管・膀胱・尿道までの尿の通り道に結石ができる病気です。
● トイレに行く回数が多い
● おしっこの色がオレンジや赤っぽい(血尿)
● おしっこをする時に痛がる様子がある
● トイレに行ってもおしっこが出ていない
結石は尿に含まれる成分から作られるため、水を飲む量が少ないと尿が濃縮されて結石ができやすくなります。
マンチカンは遺伝的に尿路結石になりやすいとされる猫種のため、毎日の飲水量をチェックしたり、食事の内容にも注意しておきましょう。
-
月払保険料¥2,120※トイ・プードル0歳70%補償プラン|保険期間:1年 | 保険料払込期間:1年
-
月払保険料¥1,550※トイ・プードル0歳ペットほけんフィット70%補償プラン|保険期間:1年 | 保険料払込期間:1年
-
月払保険料¥1,990※トイ・プードル0歳わんデイズ・にゃんデイズ70%プラン|保険期間:1年 | 保険料払込期間:1年
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2026年01月01日~01月31日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。
マンチカンの病気の予防と健康管理

半年に一度はX線やエコー検査でチェック
マンチカンは遺伝的にかかりやすい病気があるため、定期的に関節の状態や心臓の状態を検査しておくのが重要です。
X線やエコー検査などで半年に一度は健康状態をチェックしておくと、病気の早期発見・早期治療に繋がります。
日常観察で健康の変化を見逃さない
毎日猫の動きや食欲、トイレの回数や排泄物の状態をチェックしておくと、些細な異常にも気づきやすくなります。
歩行時の違和感、関節の腫れ、排尿時の異常など、気になる点があれば早めに動物病院で相談しましょう。
栄養バランスのとれたフード選定
猫の肥満は関節や心臓への負担も大きくなりやすいため、フードは高品質で低カロリーなキャットフードを選びましょう。
尿路結石などの下部尿路疾患を予防するためには飲水量も重要となるので、あまり水を飲まない場合はウェットフードで水分補給を補助するのもおすすめです。
また、運動不足にならないようにおもちゃで遊んだり低めのキャットタワーを設置すれば、関節の負担を軽減する対策をしながら肥満対策にもなります。

マンチカンの日常的なケア

耳掃除や耳の健康チェックの習慣化
マンチカンの折れ耳は通気性が悪いため、外耳炎になりやすい傾向にあります。
耳は引っ張らず優しく折れている耳をめくって、コットンや綿を足した綿棒などをしめらせて、耳奥には入れず表面についている耳垢を拭ってあげましょう。
耳掃除が難しい、不安を感じる場合は、定期的に動物病院で耳掃除してもらうのもおすすめです。
ストレス管理と快適な生活環境づくり
静かで落ち着けるような隠れ場所を作るなど、猫が安心できる生活環境づくりをしてストレスを軽減しましょう。
猫のストレスを軽減すれば、免疫力や健康の維持に繋がります。
治療費や投薬管理を事前に準備
マンチカンがかかりやすい病気には根治が難しい病気もあるため、慢性的な治療が必要になる可能性があります。
動物病院での医療費や通院計画を事前に考えて準備しておくと安心です。
猫の高額な医療費に備えられるペット保険

ペット保険とは、ペットが病気やケガをして動物病院を利用した際の治療費や手術費の一部を補填するための保険です。
ペットが病気やケガをしても、治療にかかる費用は基本的には飼い主が全額自己負担する必要があります。
ペット保険に加入していれば万一の際の経済的負担を軽減できるので、大切な家族のためにペット保険の加入を検討するのはおすすめです。
| ペット 保険 |
日本ペット | SBIプリズム少短 |
|---|---|---|
 |
 |
|
| 保険 対象 |
犬・猫
|
犬・猫・小動物・鳥類・爬虫類
|
| 猫の 保険料 (月額) |
【0歳~4歳】 ネクスト:800円 ライト:610円 ミニ:140円 ※50%補償・インターネット割引・免責額適用特約あり |
【バリュー】 0歳:3,880円 1歳:3,540円 2歳:3,160円 |
| 補償 割合 |
50%・70%・90% ※ミニプランは70%のみ |
100% ※入院・通院・手術の1日(1回)の上限金額および年間上限回数あり |
| 特徴 | 0歳~4歳まで保険料変動なしで満10歳まで加入可能 ネクストプランは歯科治療・パテラ・ガン・泌尿器疾患も補償※歯石取りは除く |
全国の動物病院が対象 休日診療費・時間外診療費も補償 スマホでいつでも保険金請求ができる |
| 見積 申込 |
||
| B24-011(240717) | JACAP202400079 |
-
月払保険料¥2,120※トイ・プードル0歳70%補償プラン|保険期間:1年 | 保険料払込期間:1年
-
月払保険料¥1,550※トイ・プードル0歳ペットほけんフィット70%補償プラン|保険期間:1年 | 保険料払込期間:1年
-
月払保険料¥1,990※トイ・プードル0歳わんデイズ・にゃんデイズ70%プラン|保険期間:1年 | 保険料払込期間:1年
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2026年01月01日~01月31日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。
マンチカンのかかりやすい病気:まとめ

マンチカンは愛らしい見た目で人気の高い猫種ですが、遺伝的に関節や心臓などの病気のリスクが高いと理解して飼育する必要があります。
定期的な検診と日常観察をしっかりと行い、病気の早期発見・早期治療をするのが重要です。
また、関節への負担の少ない生活環境を整えて、マンチカンと長く健康に過ごせるようなケアをしていきましょう。