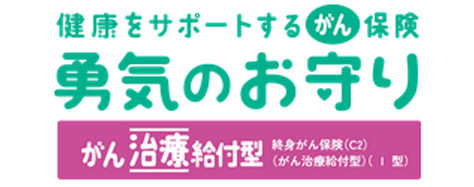- 保険
- がん保険
がん保険の一時金は確定申告でどうする?確定申告時にがん保険をどう扱うか解説


『がん保険は確定申告の時どうする?』
今回はがん保険の一時金を確定申告でどう扱うか、確定申告が必要になるケースや、課税対象になる契約形態、一時金を受け取ったらやるべき申告の手順などを解説。
おすすめのがん保険も紹介しますので、気になる方は必見です。

この記事の監修者
-
 有岡 直希
有岡 直希ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。- <保有資格>
- AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士
- この記事の編集者
- 最新記事
- グッドカミング編集部
- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。
- 20代で結婚して後悔する?20代で結婚して後悔する理由と後悔を防ぐ方法 2026.01.29
- 一生彼女ができない気がする原因は?対処法や真剣な出会いができる方法を紹介 2026.01.28
- 20代で結婚は本当にもったいない?判断材料になる婚活の始め方を紹介! 2026.01.28
この記事の目次
がん保険の一時金は確定申告が必要?

がん保険の一時金に確定申告が必要かどうか、まず支給された一時金について改めて知ってから紐解いていきましょう。
一時金とは?がん保険の保障を確認
この一時金は治療費の補填や生活費の確保に活用される現金であり、受け取り後すぐに自由に使えます。
『診断給付金』も実質的には同じ支払いに該当するので確定申告が必要か確認しましょう!

多くの保険会社では、がんと確定診断された時点で自動的に支給対象となります。
支払い条件は、約款に記された「がんの定義」に該当しているかどうかで判断されます。
では、このような一時金に対し確定申告は必須なのでしょうか?
確定申告が必要かを判断する基準
原則として、契約者・被保険者・受取人がすべて同一人物であれば、この一時金は「非課税所得」として扱われます。
- ただし、
- 受け取った人が契約者本人ではない場合
- 贈与とみなされる支払い形式である
このような状況では、所得税または贈与税の申告が求められるため、支給対象者の立場に注意が必要です。

税務署では、誰が契約して誰が給付金を受け取ったかによって課税の有無を判定しています。
医療保険の中でもがん保険は比較的非課税になりやすいですが、例外も存在するため油断は禁物です。
一時金が課税対象になる具体例
- また、
- 被保険者が死亡し、一時金を家族が受け取るような形式
このように契約形態が複雑になると、非課税扱いにならず、申告義務が発生する場合があります。
受取額が大きいと税務調査の対象にもなりやすいため、契約書の写しや支給証明書類は必ず保管してください。
金融庁や国税庁が出しているガイドラインも参考にしながら、課税の判断は慎重に進めるべきです。

確定申告が必要になるケースとは?

-
がん保険の一時金は
- 受取人が契約者でない
- 受取金額が大きい
- 医療費控除との関係
また、
受取人が契約者以外だと申告の必要性が高まる
このようなケースでは贈与税の申告が必要となり、確定申告を怠ると後日追徴課税を受けるリスクもあるんです。

また、受取人が配偶者であっても契約名義が異なると課税関係が発生するため、家族間であっても油断できません。
不明点があれば、税理士や保険会社の窓口で確認し、契約の見直しも視野に入れてください。
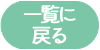
一時金の受け取り金額が大きいと目立つ
- 陥りやすいケースだと
- 複数の保険会社から同時に一時金を受け取ったのを『雑所得』とみなされる
- 契約形態が影響し『一時所得』に該当し、年間の所得額との関係で申告義務が発生する
『一時所得』とみなされた場合は50万円の特別控除を適用しても、超過分が課税対象となるため注意です!ト

このように、受取金額が大きい時ほど『保険金をどう申告すればよいのか』慎重に判断する必要があります。
税務署や専門家に相談し、収入とのバランスを考慮しながら対応を進めてください。
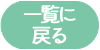
医療費控除との関係に注意
- ただし、
- 一時金は医療費の補填と見なされる
このような調整が必要になるため、医療費控除の申請時には一時金の有無を明記するのが基本です。
また、一時金の使途が生活費であっても税務上は医療費を補填する支給と判断する可能性があるため、使い道ではなく給付の目的が重視されます。
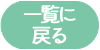
課税対象になる契約形態をチェック

これからがん保険への加入を考えている方は、確定申告で非課税になるかも含めて検討しても良いかもしれません。
ここでは『どのような契約形態が非課税になるのか』また『第三者が受け取る契約の注意点』を解説します。
一時金が非課税になる契約形態
この3者が一致している場合、保険金は「本人が自分のために加入し、自分で受け取った給付金」と見なされ、所得税の対象から除外されます。
- 逆に
- いずれかが異なっていると、税務上は第三者からの贈与または相続と判定しやすいです。
このような契約形態では、一時金を受け取る際に確定申告が必要になります。
不明確なまま受け取ってしまうと、後から税務署からの確認や申告漏れの指摘を受ける可能性もあります。
契約書の控えは手元に残し、将来的な証拠資料として保管しておくと安心です。

第三者が受け取るケースの注意点
- とくに、
- 親が契約した保険で子どもが受取人
- 配偶者に一時金を贈る形になっている
第三者に対する一時金の支払いは税務署に贈与と判定されがちで、110万円を超える額を受け取ると贈与税の申告が必要になります。
受取人を途中で変更した場合もその変更前後の契約形態によって税務上の扱いが変化します。

受け取る本人が贈与と認識していなかったとしても、税務署は契約内容を元に課税の可否を判断します。
保険会社への確認と併せて、契約形態の見直しや専門家への相談も検討しましょう。
✅複数の保険から一時金を受け取ったら?
契約形態に問題がなければ非課税となりますが、契約者や受取人が異なると課税対象に変わる可能性があります。
一時金を受け取った年が同じであれば、合算して年間の収入に計上されるため、確定申告が必要になる可能性が出てきます。
また、受取日が違っても同じ課税年度に属する場合は、全体をまとめて申告しなければなりません。
給付金明細や受取証明は、確定申告書に添付する書類としても重要な役割を果たします。

一時金を受け取ったらやるべき申告の手順

確定申告が必要かを確認する方法
判断に迷ったときは、国税庁の公式サイトにある「確定申告書等作成コーナー」や「課税対象フローチャート」が役立つでしょう。
また、最寄りの税務署に直接相談すれば、契約内容に基づいた具体的な助言を得られます。
一度受け取ってしまった一時金でも、申告を怠ると後から追徴税や延滞税が発生する恐れがあります。
もし確定申告が必要になったら以下の手順で進めましょう。
一時金を確定申告する時の手順
おすすめのがん保険
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2025年12月01日~12月31日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。
『ひとまず保険に入れそうか知りたい!』そんな方はぜひグッドカミングのLINE相談で無料診断してみましょう!


がん保険の一時金は契約形態によって課税対象になる

今回はがん保険の一時金を確定申告でどう扱うか、確定申告が必要になるケースや、課税対象になる契約形態、一時金を受け取ったらやるべき申告の手順などを解説しました。
契約者・被保険者・受取人がすべて同じであれば、基本的には非課税と見なされ、確定申告は不要です。
しかし、契約者と受取人が異なる契約や、被保険者の死亡に伴う一時金の受け取りでは、贈与税や相続税が関係してくる場合があります。
判断が難しいケースでは、国税庁のガイドや税務署の窓口での相談を活用し、確実な情報に基づいて手続きを進めましょう。
必要書類の準備や申告方法の確認も早めに行い、期限を守って対応するのが重要です。
不安な状況のなかで、経済的な支えとなる保険金を安心して受け取るためにも、正しい税務知識を身につけておきましょう。