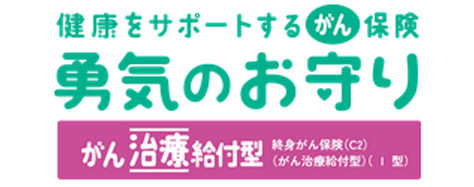- 保険
- がん保険
抗がん剤の副作用が出にくい人の特徴は?抗がん剤の副作用が出にくい人の特徴と副作用の対策を解説


『抗がん剤の副作用が出にくい人はいる?』
今回は抗がん剤治療の副作用について基礎知識や副作用が出にくい人の特徴、副作用を軽減するための工夫と対策、副作用が起こりにくい治療法などを解説。
おすすめのがん保険も紹介しますので、抗がん剤治療の副作用について知りたい方は必見です!

この記事の監修者
-
 有岡 直希
有岡 直希ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。- <保有資格>
- AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士
- この記事の編集者
- 最新記事
- グッドカミング編集部
- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。
- 20代で結婚して後悔する?20代で結婚して後悔する理由と後悔を防ぐ方法 2026.01.29
- 一生彼女ができない気がする原因は?対処法や真剣な出会いができる方法を紹介 2026.01.28
- 20代で結婚は本当にもったいない?判断材料になる婚活の始め方を紹介! 2026.01.28
抗がん剤治療の副作用とは?

抗がん剤の目的と作用の仕組み
細胞の増殖を防ぐ抗がん剤を用いた治療法。
・がんがふえるのを抑えたり
・成長を遅らせたり
・転移や再発を防いだり
・小さながんで転移しているかもしれないところ
を治療するためなどに用いられます。
引用:がん情報サービス/薬物療法(抗がん剤治療)のことを知る
がん細胞は正常な細胞と比べて、非常に早いスピードで分裂します。
抗がん剤はこの特徴を狙って、細胞分裂のスピードが速い細胞に強く働きかける仕組みです。
そのため、『分裂が活発な正常細胞』も含めて攻撃を受けてしまい、吐き気や脱毛などの副作用が生じます。
副作用が起こるメカニズム
これらの部位では日々、新しい細胞が作られているため、ダメージを受けやすくなります。
- 抗がん剤により細胞の働きに乱れが生じると
- 免疫力の低下
- 消化機能の低下
また、神経にも影響が及ぶと『手足のしびれ』や『感覚異常が現れる』場合も。
こうしたメカニズムが重なり合い、抗がん剤治療では多様な副作用が発生します。
副作用が出やすい部位とその理由
◆副作用が出やすい部位
●毛根
細胞が活発に分裂しているため、脱毛が起きやすくなる。
●消化器官や口腔内
粘膜の細胞が破壊されるため、下痢や口内炎が現れやすくなる。
●骨髄
白血球の減少につながり、感染症への抵抗力が低下。
抗がん剤治療では上記のように、細胞分裂が盛んな部位ほど副作用のリスクが高くなります。
副作用はいつから出る?タイミングの目安
副作用が出るタイミングと症状は以下のように進行していきます。
- 投与当日から翌日にかけて
- 吐き気や食欲不振
- 投与から1〜2週間後
- 白血球の減少や脱毛
そのため、治療後1週間ほどは体調の変化に細かく注意を払う必要があります。
日常生活のなかで体調に変化があれば、早めに医師へ相談する習慣を持ちましょう。
副作用の現れ方に個人差がある理由
- その違いは
- 体質
- 年齢
- 持病
- 代謝スピード
副作用の個人差は『薬を分解する酵素の働き』が人によって異なり、体内に薬がとどまる時間にも差が出るため起こると考えられます。
また、体力の有無や栄養状態によっても副作用の感じ方が変化するでしょう。
一人ひとりの身体の状態によって治療の負担が変わるため、個別に対応する姿勢が求められます。

さらに詳しく副作用の症状について知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
副作用が出にくい人の特徴
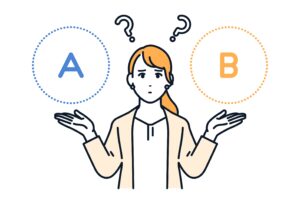
抗がん剤の副作用がどの程度、あらわれるのかは体質や遺伝的な影響が大きいです。
それでも、抗がん剤治療の副作用が出にくい人は『生活習慣が整っている』『医師との連携がスムーズ』などの特徴があります。
体質や遺伝的な影響が大きい

これは抗がん剤の成分を分解する酵素の働きが人によって違うからだったよね。
そうですね!主な要因はそこですが、体力の有無や栄養状態などの要素も含まれるので一概には言い切れません。

特定の酵素が活発な人は薬の排出が早いため、副作用が軽く済む傾向があります。
基本的には抗がん剤での治療には副作用が起こり得ると認識しておきましょう。
最近では、がん治療前に遺伝子を調べて体質に合った薬を選ぶ方法も増えています。
自分の体に合う治療を見つけるためには、医師との綿密な情報共有が欠かせません。
生活習慣が整っている人はリスクが低い
- 栄養バランスの取れた食事
- 十分な睡眠
- 適度な運動
また『腸内環境を整える』と免疫の働きを高め、副作用の緩和効果も期待できるようです。
血流や内臓機能が安定していると、薬の代謝もスムーズに進みます。
医師との連携がスムーズな人
抗がん剤の副作用をはじめ、治療に関しては症状が出始めた段階で相談できると早期対応が可能になります。
薬の種類や投与スケジュールの調整が早めにできれば、副作用の拡大も防ぎやすいです。
医師に遠慮せず、細かな変化でも報告する姿勢がとても重要となるでしょう。

安心して治療に臨むためには、担当医やスタッフの方と信頼関係を築いておきたいね!
副作用を軽減するための工夫と対策

抗がん剤治療の副作用は以下のような工夫で対策できる可能性があります。
食事の見直しで体への負担を減らす
| 摂りたい栄養素 | 避けたい要素 |
| タンパク質やビタミン、ミネラル 体力維持・副作用軽減・治療効果の最大化のために必要。 |
脂っこいメニューや刺激物 胃腸への刺激を抑えましょう。 |
-
タンパク質の重要性
●組織修復と免疫力の維持
抗がん剤はがん細胞だけでなく、正常な細胞(特に消化管・毛根・骨髄など)にもダメージを与えるため、体の修復能力が求められます。
タンパク質は筋肉や皮膚、血液、免疫細胞の材料になるため、不足すると感染症リスクが高まり、回復が遅れてしまうため、タンパク質を補える食事が重要です。
●体重・筋肉の維持
治療による食欲低下や吐き気、味覚異常で食事量が減りやすく、筋肉量が減ると体力や生活の質(QOL)も低下してしまうでしょう。
十分なタンパク質摂取は、筋肉量の維持に必要不可欠です。
-
ビタミン・ミネラルの役割
●代謝のサポート
治療中の体は代謝活動が高まり、より多くの栄養素を必要とします。
ビタミンB群やマグネシウム、亜鉛などは、エネルギー産生や酵素反応に必須の栄養素です。
●抗酸化作用(副作用の軽減)
抗がん剤は体内で活性酸素を生じさせ、正常細胞にも酸化ストレスを与えます。
ビタミンC・E、セレンなどの抗酸化物質は、こうしたダメージから細胞を守り、倦怠感や皮膚障害などを軽減する可能性があります。
●免疫力の強化
ビタミンA・C・D、亜鉛などは免疫細胞の働きをサポートし、感染症予防にも貢献。
手洗いうがいや人ごみを避けるだけでなく、食事でも免疫を高められる栄養素を摂れるようにしましょう。
-
栄養管理の工夫と重要性
●治療の継続性と回復促進を助ける
栄養状態が良好だと、副作用による治療中断を防ぎやすくなり、結果として抗がん剤治療を計画通りに進められる可能性が高まります。
治療終了後の回復もスムーズになり、生活の質改善にも寄与するでしょう。
●治療中にできる栄養管理の工夫
抗がん剤治療中は副作用から食事での栄養摂取が難しくなる可能性もあります。
そのような場合は、栄養補助食品(高タンパクゼリー、ビタミンドリンク)や医師・管理栄養士の指導のもとでのサプリメント活用も検討しましょう。
❗注意点ただし、一部のサプリメント(例:抗酸化剤の過剰摂取など)は治療効果に影響を与える可能性もあるため、医療者との相談を徹底し、栄養指導を受けたうえで摂取してください。
食事での栄養管理の際は一度に食べようとせず、回数を増やして少しずつ栄養を取り入れるよう心がけましょう。
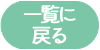
副作用の記録をつけるメリット
- 服薬時間
- 吐き気があるか
- 発熱しているか
- 食欲はあるか
医師に伝えるときも記録があれば、診察がスムーズに進みます。
変化のパターンが見えてくると、対策を立てやすくなるのでその後の治療も安心です。
自分の体と向き合うためにも、記録を習慣にすると安心感が高まるでしょう。
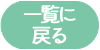
医療者との相談で薬の調整も可能に
副作用が強く出ている場合は、薬の種類や投与量の見直しが検討されます。
医師と細かく情報共有できていると、より負担の少ない方法へ変更できるかもしれません。
また、症状に応じて補助的な薬を使い快適さを保つ手段も選択肢となるでしょう。
早めの対応が治療の継続を助け、生活の質も守る結果に繋がるのです。
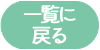

抗がん剤の副作用が少ない治療法

抗がん剤の副作用が発生するかは個人差が激しく、体質や遺伝的な部分も影響するため『副作用が少ない治療法を選ぶ』のも得策です。
副作用が少ない新しい抗がん剤の選択肢
近年は従来の抗がん剤と比べて『副作用を抑えた新薬』が登場しています。
代表的な新しい治療法が以下のふたつです。

✅分子標的薬
従来の薬と異なり、がん細胞の特定の構造や機能を狙い撃ち。
がん細胞だけに作用しやすいため、副作用を抑えながら高い治療効果が期待されます。
✅免疫チェックポイント阻害薬
免疫細胞の働きを回復させる仕組みを持っている薬です。
これにより、体内の免疫力を使ってがんと戦う力を引き出せます。
医師に最新の薬の情報を確認し、自分に合う治療法を検討してみてください。
点滴以外の方法での治療も検討を
飲み薬であれば通院回数が減り、精神的な負担も軽くなります。
また、局所に直接薬を届ける方法も『副作用を抑える手段』として注目されているようです。
治療の形を変えられれば、身体への影響を減らせる可能性が高まります。
副作用に配慮した個別化治療とは
これは一人ひとりに合う薬の種類や量を見極めて使う治療法です。
副作用のリスクを最小限に抑えながら、がんに対してしっかりと効果を出す設計が可能です。
治療前に遺伝子検査を行い、体に合う薬を選ぶ流れが一般的になりつつあります。
最適な治療を受けるためには、事前に選択肢を知っておく『情報収集』が有効ですよ!

おすすめのがん保険
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2025年12月01日~12月31日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。
副作用が出にくい人を目指すには

今回は抗がん剤治療の副作用について基礎知識や副作用が出にくい人の特徴、副作用を軽減するための工夫と対策、副作用が起こりにくい治療法などを解説しました。
抗がん剤の副作用には個人差があり、まったく同じ治療でも反応が異なります。
- 副作用の軽減には
- 普段の食事
- 睡眠
- ストレス管理
また『新しい治療法』や『個別化医療』を取り入れると、より自分に合った選択ができるようになります。
安心して治療を受けるためには、正しい知識と周囲のサポートを活かして行動するのが大切です。