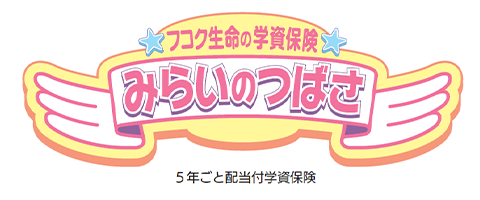- 保険
- 学資保険
学資保険と貯蓄どっちが正解?教育資金の効率的な貯め方を徹底比較


学資保険は貯蓄代わりに使えるって本当?
学資保険と普通の貯蓄、どっちが効率的?
教育資金は、学資保険と貯蓄どちらにすべき?
子どもの教育資金を確保するため、貯蓄か学資保険か迷う方も少なくありません。
この記事では、学資保険の仕組みや貯蓄との違いを比較し、あなたに合った資金準備の方法をわかりやすく解説します。
この記事の監修者
-
 有岡 直希
有岡 直希ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。- <保有資格>
- AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士
- この記事の編集者
- 最新記事
- グッドカミング編集部
- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。
- 犬の抗がん剤治療の費用はどれくらい?ペット保険は使える?万一への備え方 2026.01.09
- オーネットにサクラはいる?サクラがいるのかオーネットの実態を徹底調査! 2026.01.08
- 20代の婚活はオーネットがおすすめ?20代割があるオーネットで婚活成功 2026.01.07
この記事の目次
学資保険と貯蓄の違い
学資保険とは、子どもの教育費を目的に契約する保険商品です。
貯蓄は特定の目的や用途はなく金融機関にお金を預けるのみですが、学資保険には保険会社が設定する返戻率や保障内容があり、契約期間も定められています。
✅任意で設定可能、子どもが高校や大学へ入学・卒業するタイミングが一般的
✅満期を迎えると被保険者である子どもが保険金を受け取れる仕組み
対して、貯蓄は必要になったら引き出せる自由度があり、預け入れの期間や金額も柔軟に設定できます。
自由度の高い貯蓄と保障が安心な学資保険

預け入れの期間や金額が自由なのは貯蓄ですが、学資保険には万が一に備えた保障機能がついています。
万が一、契約者である親が亡くなったり、重篤な病気にかかり働けなくなった際に保険料が免除され、満期に合わせて保険金が受け取れる仕組みです。
教育資金を効率的に準備する観点で比較

教育資金を計画的に準備するためには、効率と安定性が重要なポイントです。
✅計画的に積み立てたいなら学資保険
✅運用の自由度を重視するなら貯蓄
将来どの程度の教育資金が必要かを計算し、貯蓄と学資保険どちらが効率的かつ無理なく続けられるかを見極めましょう。
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2025年12月01日~12月31日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。
学資保険と貯蓄のメリット・デメリット比較
学資保険と貯蓄を検討するにあたり、両者のメリットとデメリットを整理してみましょう。
学資保険
- メリット
-
- ・契約期間の満期まで保険料を支払うと、100%以上の返戻率が期待できる
- ・万が一契約者が死亡したり重篤な病気にかかった際には保険料の支払いが免除
- デメリット
-
- ・長期契約前提のため、途中解約は元本割れの可能性あり
- ・満期前の引き出しは不可
貯蓄に比べると柔軟性が低いため、資金の流動性を重視する家庭においては慎重な判断が求められます。
100%以上の返戻率とは、支払った保険料よりも多くの返戻金を受け取れるのです。
保障機能も充実しているため、万全な教育資金準備を目指す家庭にとって安心感があるでしょう。
貯蓄
- メリット
-
- ・使い道の自由度が高く、いつでも引き出せる
- ・積立額や期間を自分で自由に設計でき、元本割れのリスクがほぼない
- デメリット
-
- ・利回りが低い
- ・計画的な積み立てが難しい
貯蓄は教育費に限らず、急な出費や家計の変化にも柔軟に対応できます。
自由度が高い反面、自発的に続ける意思がないとつい無駄遣いをしてしまい、積立が続かないケースも。
学資保険のように返戻金はなく、現在の金融市場では得られる利息も少ないため資金を増やす効果は限定的です。
学資保険と貯蓄に向いている人の特徴
学資保険が向いているのは
✅計画的に貯めたい
✅リスク回避したい
人です。
学資保険は一定額を強制的に積み立てるため、貯蓄の習慣がない人や無駄遣いの不安がある人に適しています。
保障機能も充実しており、病気やケガなど万が一の際にも教育資金を確保できる安心感があります。
リスクを避けて確実に教育資金を準備したい人には、学資保険が向いているといえるでしょう。
貯蓄が向いているのは「柔軟に資金を動かしたい人」「利便性を重視する人」
貯蓄は自由に積立額を設定できるほか、必要に応じて資金を引き出せるため、生活スタイルが変化しやすい人に適しています。
学資保険とは異なり教育費以外にも使えるため、幅広い目的に対応できる点が魅力です。
自由度と使い勝手を重視し、状況に応じて積立金額を調整したい人は、貯蓄のほうが合っているかもしれません。
家計の安定度や貯蓄習慣によって選び方が変わる
学資保険と貯蓄のどちらを選ぶかは、家計の収支状況によっても大きく左右されます。
たとえば、サラリーマンや公務員などのように安定した収入があり、毎月一定額の積立ができる家庭は長期契約の学資保険に向いています。
一方、自営業やフリーランスなどのように、月によって収入が不安定な家庭では、貯蓄の柔軟性を活かすほうがリスクを避けられる可能性もあるでしょう。
学資保険と貯蓄の使い分け方と選び方
リスク分散として併用する方法
学資保険と貯蓄は、どちらか一方に絞らず併用も効果的です。
たとえば、学資保険で一定額の教育費を確保しつつ、毎月少額でも貯蓄しておけば想定外の出費にも備えられます。
ライフプランと教育資金目標に合わせる
子どもの進学時期や進路によっても教育資金の目標額は変わってきます。
まずは将来の進学予定や留学希望などをもとに、必要な金額を具体的に計算しておきましょう。
そのうえで、学資保険と貯蓄の割合や使い方を検討するのが効果的です。
ライフプランに沿って組み合わせを調整すれば、無理のない資金計画が立てられます。
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2025年12月01日~12月31日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。
家計の収支や貯蓄状況を基準に判断
将来のためとはいえ、保険料や積立金の支払いがあまりにも高額で家計を圧迫してしまうと本末転倒です。
まずは現在の収支を記録し、どの程度の金額を教育資金に回せるかを確認しておきましょう。
収支の安定性が高ければ、学資保険のような定額支払い型でも無理なく続けられます。
一方、収入の波がある家庭では、柔軟に対応できる貯蓄のほうが適している場合があります。
学資保険ではなく低解約返戻金型の終身保険を活用するのもあり
近年、低解約返戻金型の終身保険を学資保険の代替手段として利用される方が増えています。
✅教育資金として使わなくても解約せずにそのまま終身保険として継続保有でき、将来的な保障の確保や資産形成の手段として活用の幅がある※学資保険は選択肢がない

学資保険と終身保険、どっちがいいんですか?
返戻率重視なら学資保険、柔軟性や保障を重視するなら終身保険がおすすめです。
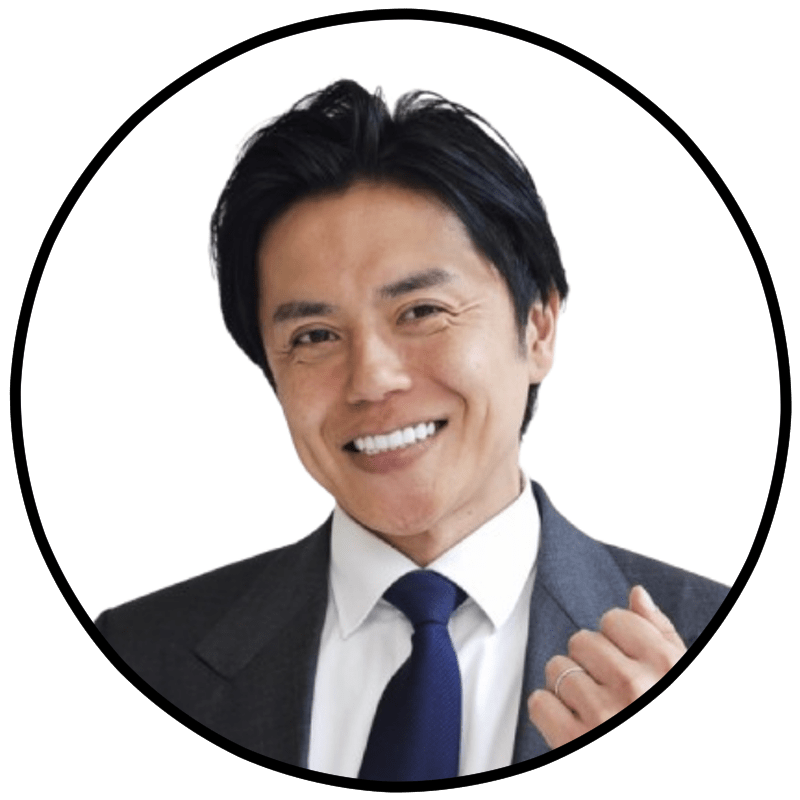
家族構成やライフプランによっても必要な保障のあり方は異なるため、迷っている方は一度保険のプロに相談してみましょう。
学資保険と貯蓄は目的に応じてバランスよく使おう
教育資金の準備にはさまざまな方法があり、たとえば学資保険には充実した保障や計画的な資金の積み立て、貯蓄には積み立てや引き出しの柔軟性といった強みがあります。
それぞれの特長を理解したうえで、リスクを分散させながら効率よく積み立てれば、安心して将来を迎えられます。
まずは目標を設定し少しずつ行動に移していきましょう。