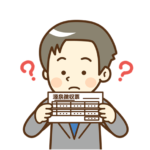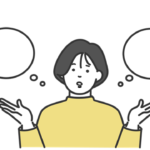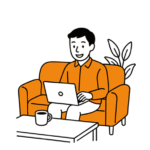- 保険
- 収入保障保険
収入保障保険の保険料は確定申告で控除できる?申告の流れと注意点を解説


収入保障保険の保険料は確定申告で控除できる?控除対象になるのは誰?
収入保障保険に加入していると、確定申告が必要なのか気になる人は多いですよね。
給付金の扱いや保険料控除の申請など、確定申告と収入保障保険の関係は意外と複雑です。
この記事では、どのような人が確定申告の対象となるのか、控除の受け方を解説します。
- この記事の編集者
- 最新記事
- グッドカミング編集部
- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。
- オーネットは気持ち悪い?オーネットの気持ち悪いといわれる評判を徹底解説 2026.01.09
- 犬の抗がん剤治療の費用はどれくらい?ペット保険は使える?万一への備え方 2026.01.09
- オーネットにサクラはいる?サクラがいるのかオーネットの実態を徹底調査! 2026.01.08
この記事の目次
収入保障保険と確定申告の関係とは

収入保障保険は、契約者が亡くなった場合に遺族へ毎月一定額の給付金が支払われる保険。
収入保障保険から支払われる金額が「所得」とみなされるケースでは、確定申告が必要になるケースがあります。
受取人が保険料を支払っていたかどうかによって、課税区分が異なり、所得税や相続税の対象になる場合も。
税務上の扱いは契約内容によって変わるため、受け取った金額や契約の仕組みを整理し、必要に応じて税理士へ相談しましょう。
確定申告とは?
確定申告とは、1年間に得た所得を税務署へ届け出て、所得税を正しく清算する制度です。
申告期間は毎年2月中旬から3月中旬までと決まっており、必ず期限内に提出しなければなりません。
自営業やフリーランスのほか、給与以外の収入が一定額を超えている会社員も申告対象に含まれます。
医療費控除やふるさと納税の還付を受けるためにも必要な手続きとなるため、対象者は忘れずに準備を進めましょう。
会社員と自営業での違い
会社員は勤務先で年末調整が実施されるため、基本的に確定申告をする必要はありません。
収入保障保険の保険料も、ほかの生命保険とあわせて年末調整で控除されるのが一般的です。
一方、自営業やフリーランスは年末調整が受けられないため、生命保険料控除を含めたすべての申告作業を自分で済ませる必要があります。
保険料の控除を正確に反映させるには、保険会社から送られてくる控除証明書を確定申告書に添えて提出しましょう。
収入保障保険の保険料は生命保険料控除の対象

収入保障保険の契約者かつ保険料を負担した人が、生命保険料控除を受けられます。
保険契約が複数ある場合でも上限は変わらないため、保険の分類を確認し控除の重複を避けましょう。
同じ収入保障保険でも加入時期によって控除額が変わります。
新制度(平成24年1月以降契約)の一般生命保険料控除は、年間の支払額に応じて以下のとおり最高4万円が控除。
| 年間払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 払込保険料全額 |
| 2万円超4万円以下 | 払込保険料×1/2+1万円 |
| 4万円超8万円以下 | 払込保険料×1/4+2万円 |
| 8万円超 | 4万円(上限) |
旧制度(平成23年12月以前契約)においては、上限を5万円として以下のとおり控除可能。
| 年間払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2万5,000円以下 | 払込保険料全額 |
| 2万5,000円超5万円以下 | 払込保険料×1/2+1万2,500円 |
| 5万円超10万円以下 | 払込保険料×1/4+2万5,000円 |
| 10万円超 | 5万円(上限) |
収入保障保険の給付金は課税対象になる?
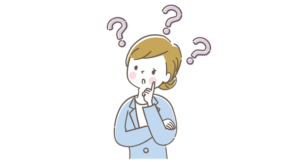
死亡保険金の受け取りは原則課税対象
収入保障保険で受け取る死亡保険金は、課税対象として所得税・住民税・相続税・贈与税のいずれかに該当します。
相続人が受取人に指定されているときは、相続税の非課税枠が適用され、一定額までは税負担が発生しません。
非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の人数」で計算され、それを超える部分のみが課税対象となります。
誰を受取人に指定するかにより、課税額や税の種類が大きく変わるため、契約時にしっかり確認しておきましょう。
就業不能給付金は非課税
病気やケガに伴う就業不能状態に対する給付金は、労働の対価ではないため原則として非課税となります。
ただし、非課税かどうかは保険の種類や契約内容によって異なるため、事前に確認しておくのが安心です。
一時金・年金形式での受け取りによる課税の違い
収入保障保険の給付金は、一時金か年金形式のどちらかを選べます。
一時金で受け取ると「一時所得」に分類され、計算式に基づいて所得税の対象となります。
年金形式を選ぶと「雑所得」として毎年の所得に加わり、税負担が年単位で発生。
税額や納税の時期に違いがあるため、生活設計に合わせて受け取り方法を見直しましょう。
収入保障保険の確定申告時の注意点

保険会社からの控除証明書は保管
収入保障保険の保険料を生命保険料控除に含めるには、保険会社が発行する控除証明書を提出しなければなりません。
証明書を紛失すると再発行に時間がかかるため、手元に届いた時点で保管場所を決めておくと安心です。
最近では、マイページから控除証明書をダウンロードできる保険会社も増えています。
紙の書類が届く前にデータで確認できる場合もあるため、各社のサービス内容を事前にチェックしておきましょう。
他の保険との併用控除上限に注意
生命保険料控除は、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つに分類。
それぞれの区分で控除される金額の上限は4万円となっており、合計で最大12万円までが所得控除の対象にあります。
ひとつの区分に集中して加入すると、他の枠が使われず控除額が最大限にならないケースも。
複数の保険契約を持っている方は、どの保険がどの区分に該当するかを確認しましょう。
支払っている保険料を把握する
生命保険料控除を有効に使いたいなら、現在の契約で年間いくら保険料を支払っているかを明確に把握するのが大切です。
控除枠に余裕がある場合、契約の増額や保険の見直しを検討すれば、より高い節税効果につながります。
家族構成や世帯収入の違いにより、最適な保険の組み合わせは人それぞれなので、シミュレーションツールなどを活用しましょう。
確定申告が必要な対象者と申告方法

年収2,000万円超・副業所得のある会社員
給与を受け取っていても、年収が2,000万円を超えている場合や本業とは別に得た副業所得が年間で20万円を超えている人も確定申告の義務が生じます。
申告漏れを防ぐためには、1年間の所得や控除を定期的に記録し、整理しておくと安心です。
該当する人は、確定申告の期間を事前に確認し、余裕を持って準備を進めましょう。
自営業者やフリーランス
事業所得を得ている自営業者やフリーランスは、毎年確定申告を必ず提出しなければなりません。
青色申告を選択すれば、特別控除によって課税所得を大きく減らせるため、税負担の軽減が期待できます。
正確な記帳や書類の準備が必要となるため、経理に不安がある場合は税理士へ相談するのが安心です。
税務署の無料相談窓口を活用する方法もあるため、早めにスケジュールを立てて準備を始めましょう。
e-Taxや税務署での申告方法
確定申告の提出方法は、書面での郵送またはe-Taxを使ったオンライン申請のどちらかから選択できます。
青色申告を選んだ場合は「青色申告決算書」、白色申告であれば「収支内訳書」の作成しなければなりません。
生命保険料控除などを申請するには、保険会社が発行した控除証明書も提出書類に加える必要があります。
マイナンバーカードとICカードリーダー、電子申告に対応したパソコン環境が整っていれば、自宅からe-Taxでの提出も可能です。
提出期限に間に合うよう、必要書類の準備は早めに済ませておきましょう。
収入保障保険の加入者は確定申告や年末調整を忘れずに
収入保障保険は、万が一の収入減少に備える役割だけでなく、税金面でも有利な制度。
生命保険料控除や給付金の非課税制度を正しく理解すれば、税負担を軽くできる場面も増えてきます。
税制を活かせば家計の安定にもつながるため、契約前に仕組みを把握しておくと安心です。
控除対象や給付条件を明確にし、自分のライフプランに合った使い方を検討してみましょう。